| 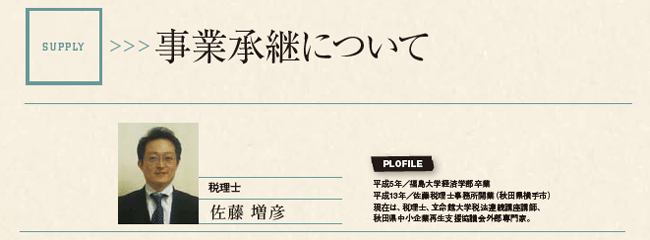
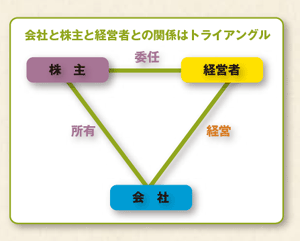 中小企業の事業承継が脚光を浴びています。一般に事業を承継する相手先には、自分の子供等の親族、従業員や古参の役員、そして、同業他社などまったくの第三者へのM&Aが考えられます。しかし、ほとんどの社長さんは自分の息子への事業承継を王道と考えるようです。 中小企業の事業承継が脚光を浴びています。一般に事業を承継する相手先には、自分の子供等の親族、従業員や古参の役員、そして、同業他社などまったくの第三者へのM&Aが考えられます。しかし、ほとんどの社長さんは自分の息子への事業承継を王道と考えるようです。
事業承継は、息子を会社の社長にするだけと考えるかもしれません。確かに、経営者にするだけならば、息子さんを代表取締役にすれば足ります。でも、会社を経営するということと、会社を所有するということは違います。株式を所有しない社長では、会社の経営方針について株主の意向に従う必要があり権限が十分ではありません。「役職」と「株式」の二つがそろって、初めて息子さんは経営者になれます。株式を全く持たない代表者では、安定性に欠けます。また、会社の敷地には、概ね、個人の資産が含まれていて、事業経営に不可欠なケースを多く見受けます。このように考えると、(1)役職と、(2)株式と、(3)会社の敷地は、会社にとって、「経営の3種の神器」といえます。
1. 社長にするまでの役職を考える (3 種の神器 その1)
「15年後には70歳になるし、遅くてもこの年齢までには会社を引退したい」。このように考えたとき、息子さんを社長にするまでに、どのような経験を積ませればよいのでしょうか。
これは表面的には代表取締役になるまでの役職の問題ですが、営業、労務管理、そして資金繰りの知識はもちろんのこと、何よりも本人の成長が欠かせません。また、世間様への認知の問題でもあります。自身の年齢と後継者の年齢、それに、事業承継を終えるときの自身の年齢と後継者の年齢を下記のように記入すると、何歳頃までに後継者をどう育てる必要があるのかが明確になります。
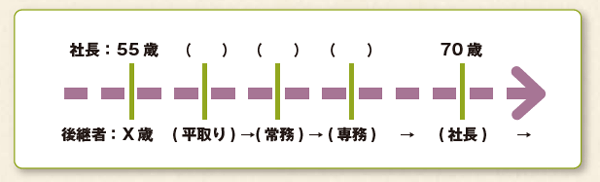
社長になるまでに、すべての役職を経験しないといけないわけでありませんが、準備期間として、社長になる前の数年間は役員にしておく必要があります。役職が変わってくる段階では税務の問題も出ます。①後継者の役員報酬の税務問題と、②社長の退職金の税務問題です。役員になると、賞与を支給しても原則として税務上の経費として認められません。一定の要件を満たす場合には、賞与支給が認められますが、従業員と役員は、まったく立場が違うのだということを伝えるためにも、役員になった息子さんへの賞与支給はあまりお勧めしません。また、役員への退職金は一般に支給金額が大きいために、税務上も支給金額・支給方法・支給時期等について慎重な検討が必要になります。受け取る側としては、退職所得は非常に税務上優遇されており、例えば23年間会社の役員を務めた方が1000万円の退職金を受け取るときにかかる源泉所得税は0円です。
2. 株式の移転はどうすべきだろうか (3 種の神器 その2)
子供を役員にするとき、会社経営の責任感を養うため自社株をいくらか持たせるケースがあります。ここで注意すべきなのが贈与税です。暦年贈与による贈与税の非課税枠は、110万円です。この金額を超えて株式を贈与すると贈与税が課税されます。110万円の判断基準の元となる株価は、いわゆる簿価ではなく、税務上の時価となります。
ある程度まとまった株式を贈与する場面では、相続時精算課税の検討も視野に入れます。いったん相続時精算課税制度を選択すると、以降はその人に対する贈与に暦年贈与を利用できませんので注意します。平成21年度税制改正により、自社株の贈与にも納税猶予が利用できるようになりました。これまでより自社株の生前贈与が容易になります。
ところで、株式が会社の古参の従業員や役員に分散しているケースがあります。中小企業の場合では、株式の譲渡に取締役会の決議が必要なケースがほとんどです。それでも相続については原則として譲渡の承認決議が不要なため、株式をそのまま放っておくと、現在の所有者からその子供の世代へ移転して分散してしまう危険性があります。現社長の責任で株式を買い集める対応が求められます。できることなら株主間の話し合いによることが望ましいのですが、中にはなかなか話し合いがつきにくいケースもあるようです。平成18年から施行された会社法では、株式に一定の特色を持たせることで有効に議決権を確保することが容易になりました。話し合いが揉めるようならば、会社法を活用した対策も検討します。
3. 個人所有する事業用財産の移転について考える (3 種の神器 その3)
 事業で利用している財産ですから、当然に後継者に財産を承継させたと考える経営者さんが多いようです。生前に移転するのであれば、贈与するか譲渡するかのいずれかが選択肢になります。ただし、税金の問題を避けて通れないために、不動産の移転については、相続まで放って置くケースが多いようです。 事業で利用している財産ですから、当然に後継者に財産を承継させたと考える経営者さんが多いようです。生前に移転するのであれば、贈与するか譲渡するかのいずれかが選択肢になります。ただし、税金の問題を避けて通れないために、不動産の移転については、相続まで放って置くケースが多いようです。
自分に相続があった後についても、「特定の人間に財産を」となると、遺言の利用を検討します。遺言書として利用されるのは自筆証書遺言か公正証書遺言ですが、偽造リスク、紛失リスク、あるいは形式不備のリスクを考えると、公正証書遺言がお勧めです。遺言というと、タブーな感じもしますが、平成18年の遺言公正証書の作成件数は全国で7万件あり、20年前の約10倍です。社会は確実に変化しています。
以上、「経営の3種の神器」の移転について簡単に説明してきました。移転にあたり、最も注意すべきことは事業を継がない子供たちへの配慮です。相続人には、兄弟姉妹が相続人となるケースを除き、遺留分という最低限の相続権があります。社長の財産が後継者にばかり集中してしまって、他の相続人たちが自己の遺留分について満たせない状況が生じると、遺留分の減殺請求をする可能性が生じます。
こうなると、せっかくの事業承継対策が水泡に帰すばかりでなく、財産の相続をめぐって大事な子供たちが争う羽目にもなりかねません。将来に無用な争いを引き起こさないような配慮が欠かせないのです。息子への事業承継は、社長さんにとっては王道でも、決して平坦な道ではないようです。
|
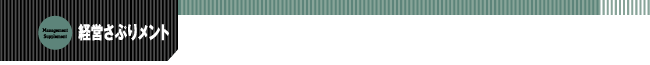

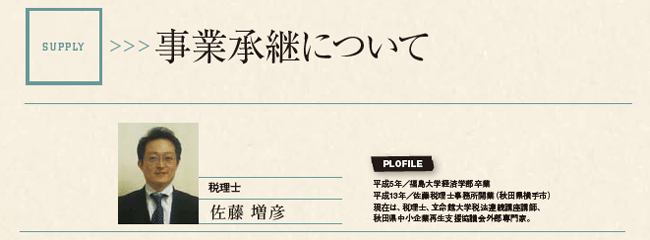
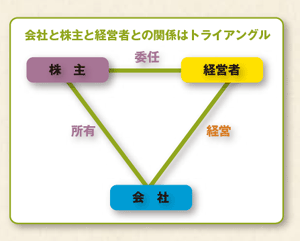 中小企業の事業承継が脚光を浴びています。一般に事業を承継する相手先には、自分の子供等の親族、従業員や古参の役員、そして、同業他社などまったくの第三者へのM&Aが考えられます。しかし、ほとんどの社長さんは自分の息子への事業承継を王道と考えるようです。
中小企業の事業承継が脚光を浴びています。一般に事業を承継する相手先には、自分の子供等の親族、従業員や古参の役員、そして、同業他社などまったくの第三者へのM&Aが考えられます。しかし、ほとんどの社長さんは自分の息子への事業承継を王道と考えるようです。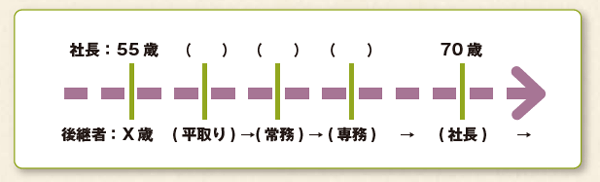
 事業で利用している財産ですから、当然に後継者に財産を承継させたと考える経営者さんが多いようです。生前に移転するのであれば、贈与するか譲渡するかのいずれかが選択肢になります。ただし、税金の問題を避けて通れないために、不動産の移転については、相続まで放って置くケースが多いようです。
事業で利用している財産ですから、当然に後継者に財産を承継させたと考える経営者さんが多いようです。生前に移転するのであれば、贈与するか譲渡するかのいずれかが選択肢になります。ただし、税金の問題を避けて通れないために、不動産の移転については、相続まで放って置くケースが多いようです。