
 (株)くらた代表の倉田潤一社長
「タナからぼたもちでした。動機が自社開発の商品ではなく、安藤さんが新しい店を出すので何か新商品をつくってくれと頼まれて生まれたソフトクリームです」 全国的にもめずらしい商品らしく、テレビの『ズームイン!! 朝!』にとりあげられたりして、「しょうゆソフト」はたちまち有名になった。味噌・醤油をキーワードにした、半年間の開発成果である。
この「奥羽本線北上商(あきない)戦略」ともいうべき、果敢な店舗展開はいったいどこからくるのであろう。老舗同士の対抗意識、新しい洋菓子店の台頭、大型店の参入など考えられる……。 「ゴーイング・マイ・ウエイですよ」と笑う倉田さん。創業150年になろうとする老舗の自信と余裕ともとれるが、きびしい現代社会をこうしたたゆまない商(あきない)戦略で闘うには、言うに言われない辛酸も味わったに違いない。 「30年近く前、秋田市で初めてくらたの商品を置いてもらおうとしたオヤジ(先代・現会長)は、交渉先の店でことごとく断わられてかなり苦労したらしいです。田舎の菓子は売れないからと言われた。気を落として歩いていたら、日赤病院の前のヤブ地に不動産の看板が立っていたんです」 金策にかけずり回ってなんとか開設にこぎつけた初の秋田店は、こうして偶然に誕生した。秋田での無念と高揚が奥羽本線北上の展開を、先代に実践させたのかもしれない。この秋田での先代の経験は、さらに商売上のあるヒントをもたらした。立地が大病院の隣とあって集客力は群を抜いたのだ。その後、この業界では「病院のそば」が立地条件の最優先の1つになったほどである。
「よい材料、よい技術、よい接客技術。これが当社の目標です」 つまり、最高のものに近づこうとする姿勢。たとえば、材料は極力地場産のもの、国産のものを使いたいが、テストをくり返した結果、品質や供給量にムラがあったり、コストが高くついたり、菓子づくりにとって安定性に欠けるものは他産地に頼らざる得ない。和菓子の生命ともいわれる主材料の小豆は北海道、備中から仕入れ、自家製餡をしているという。 技術については、倉田さんが自ら商品開発の先頭に立ち、専任スタッフとともに研磨を重ねるほか、5年ほど下積みを重ねた職人を東京の菓子店へ修行に出すことでレベルをあげている。そうして世に送り出した商品が「銘酒物語」や「とっぴんぱらりのぷう」、「通小町」「姉こもさ」などだ。とくに酒ゼリー「銘酒物語」は、東北の灘といわれた酒どころ湯沢にちなんだ傑作。アルコール分3%のところがミソだ。1%のものは全国にあるが、これくらい刺激があるのはめずらしく、しかも酒が飲めない人でも口にすることができる。 「新しい売れ筋の商品は、私のアタマではついていけないですから、JC業種別部会で知り合った東京や大阪の先輩からまるごと教えてもらうんです。そのほうが成功率が高い」 しかし、テラミスやカヌレなどマスコミで喧伝された商品は火がつくのが早いが、すたるのも早いという。最後にものをいうのは、やはり老舗の商法なのか。ズバリ、ヒット商品の勘どころを聞いた。 「こればかりは出してみないと、わかりません」
 ヒット商品の酒物語など
倉田さんの趣味は食べることだという。研究を兼ねて食べ歩く。
|

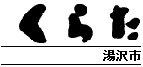


 本店のほかに秋田店、横手店、十文字店、駅前店(湯沢市)、保戸野店(秋田市)、川尻店(秋田市)、山王店(秋田市・フランス料理レストラン)、千石町店(湯沢市)、角館店がある。
本店のほかに秋田店、横手店、十文字店、駅前店(湯沢市)、保戸野店(秋田市)、川尻店(秋田市)、山王店(秋田市・フランス料理レストラン)、千石町店(湯沢市)、角館店がある。