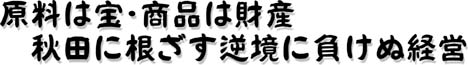全国的にも知名度が高い八郎潟。この地は明治時代から「つくだ煮」製造・販売のメッカであった。つくだ煮業界に大きな影響を与えた湖の干拓。こうした逆境にも負けず、業容を拡大してきた(株)安田つくだ煮商店。今回は、同社の社長、安田政次さん(58歳)に話しを聞いた。  「(株)安田つくだ煮商店」の社長 安田 政次 氏
こうして、小売以外に卸の販路も開拓した当社の経営は盤石かと思われた。そんな矢先、昭和32年に八郎潟干拓事業スタートという転機をむかえた。 昭和41年、当社4代目の当主である、現社長の安田政次さんの入社と時を同じくして、八郎潟の干拓が完了。湖面積が5分の1に減少したことに伴い、漁獲高が激減した。干拓以前、同町には当社の他に5社程の同業者が存在したが、つくだ煮だけを生業とすることができなくなり、転廃業していった。 そして、この激動の時代を乗り越え、生き残ったのは、同町では当社のみとなった。 以前と同様に出荷できる程の生産もできず、漁獲高も少ないため、原料価格も高騰。産地間価格競争にも勝てなくなった。 この時、安田さんに「当社の職人が丹精込めて作った商品、干拓で激減した魚を大事に売らなければ」という意識が芽生えた。そして「価格は高くなろうとも、しっかり時間と手間暇をかけ、お客様に提供しよう」と決意。限られた原料を有効に活かすため、県外への卸をやめ、県内をターゲットにした小売へと商売の比重移行を決断した。
 消費者には、原料の産地ではなく、魚自体のおいしさ、味付け、製法等が「八郎潟のつくだ煮」と認知されており、その人気は高く根強い。県内業者のつくだ煮生産量は、食の健康志向の高まりを背景に、増加し続けており、今後も着実な伸びが期待される。
第1号店の「おみやげの安田」は昭和41年、つくだ煮の直販部門強化と、当時、余剰となっていた従業員を、何としても雇用していきたいとして、八郎潟町の国道7号線沿いに出店した。あくまでも地元住民をメインターゲットに、工場から直結して、造りたてのフレッシュな製品をタイムリーにお届けすることを意識している。折り良く、高度経済成長期、モータリゼーションの波で客足も伸び、業績は順調な推移を見た。 その後、県産品、飲料、食品と扱い品目を増やし、地元顧客をはじめ、観光客、ドライバーまでをターゲットにした店舗へと変貌を遂げ、現在にいたっている。 秋田市にある市民市場店は、毎食卓向けに低価格のつくだ煮を取り扱い、気軽に食べていただける雰囲気づくりに努めている。当社で取り扱うつくだ煮は多種多彩だが、その中でも「シラウオ」、「ワカサギ」、「イカ」が人気ベスト3だそうだ。 一方、本金西武店では、高級志向のニーズにも応えられるよう、日頃なかなか入手しづらい「稚アユ」、「子持ちワカサギ」といった高級つくだ煮を品揃えし、当社商品のブランドイメージアップのための店舗と位置づけている。 現在、県内各スーパーなどから出店の要請が相次いでいるが、「当社の商品は手作りで高価なため、よそと同じ価格競争を望まれても対応できない」と断り続けている状況だそうだ。友人からは、もったいない話といわれているが、「貴重な商品を大事に取り扱える店、職人が一生懸命に作ったつくだ煮を、それ相応の価格で売れるようでなければ出店しない」と安田さんの店舗出店に対する経営方針はゆるぎない。

安田さんは、お客様のニーズを発掘し、オリジナルサービスを見出すために、自ら店頭にでて接客することをかかさない。 「秋田の商業は、現状を憂いながらも、どうすればいいかという結論が導き出せないでいる、処方箋の無い末期ガンのような状態だ。街には人や物があふれ、衣服ひとつを考えても、これから一生買わなくても暮らしていける程である。要らない物を買っていただくためには、ハード、ソフトの両面で自分のオリジナル性、強みを持つべき」と語る。 これに触発された従業員も、隣の店と同じ商品が並んでいる時、当社の商品を買ってもらうためにはどうしたらいいのかを、自らの力で考え出そうと努力し続けている。その1例として、つくだ煮を作り続けて50年余という職人の発案によって、若者のニーズとつくだ煮の伝統をミックスした「スナックつくだ煮」を創り出した。これは、全国水産加工たべもの展において水産庁長官賞を受賞。また、つくだ煮の本場でもある、大阪府知事賞なども受賞し、様々なユニークな商品を送り出しているという。 「安田のつくだ煮工房」と銘打ち、経営・商品・サービスなどのオリジナル創出に、全員で取り組んでいる。ここに働く一人ひとりがマイスターであり、正に工房と呼ぶにふさわしい店と思われた。
|