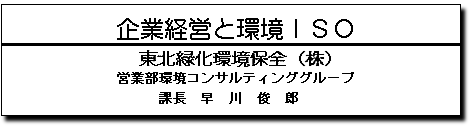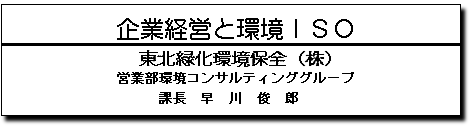|
現在、地球の環境を保全し維持することは、世界的な関心事であり、企業経営においても、当然、この視点が重要なテーマとなってきています。それゆえ、あらゆる企業に、環境問題への自主的な取り組みが求められています。そのひとつの手法である環境ISO(ISO14000シリーズ)についてご説明します。
1.環境マネジメントシステムとは?
環境マネジメントシステムは、既存の経営が環境に与える影響を把握した上で、環境負荷を低減させるための方針と目的・目標を明確化し、これを実現するために必要な仕組みをつくり、実行し、その結果を反省・評価し、さらなる環境負荷低減のための諸活動を推進するものです。これは、まさに目標管理制度なのです。企業の一般の経営システムは、人事、財務、購買システムなどたくさんありますが、それらと同じ経営システムの一つなのです。
|
| ● |
広域な適用性を持つ。(あらゆる国、あらゆる業種、あらゆる規模の組織が対象) |
| ● |
非関税貿易障壁とはしない。 |
| ● |
適合の証明としては、第三者認証審査でも、組織自らの自己宣言でも良い。 |
| ● |
客観的に監査可能な要求事項に限定している。 |
| ● |
環境パフォーマンスの基準は設定しない。 |
| ● |
最良利用可能な技術を奨励している。 |
|
2.今なぜ、企業に環境ISOが必要なのか?
この環境ISOが、なぜ企業経営に必要なのかは、どのような背景から成立したかをみれば明らかです。
1991年に「持続可能な開発のための経済人会議(BCSD)」が開催されました。その結果、企業の持続可能な開発のため「環境管理のための国際規格」が必要と確認されました。そして、その要請を受けISOが検討を開始しました。
BCSDの報告書は、まさに環境ISOの原点であるといえます。(囲み参照)
|
| 新しい社会背景の出現 |
| ● |
持続可能な開発のためには、環境保全と利潤追求という二つの課題を同時に達成するような方向に企業の意思決定を切り替えていかねばならない。 |
| ● |
社会的背景に焦点を当ててこの問題を考えていくことこそ、経営者にとって何よりの役割である。 |
| 持続可能な開発のビジョン |
| ● |
経営者は環境的に持続可能でなければ長期的な経済発展は望めないということを自覚する。 |
| ● |
給与によってだけではなく問題意識を植えつけることによって、従業員の能力開発と生産性向上を実現する。 |
| 新しい市場のための新しい経営戦略 |
| ● |
ビジョンを戦略に結びつけ、行動計画として実行しなければ何にもならない。そのためには、しばしば事業活動のプロセスとシステムを見直し、再編成し、再構築することが必要となる。 |
| 成果と測定と環境監査 |
| ● |
持続可能な開発という面で、企業として達成すべき目標を定め、これを組織的に、定期的に、客観的に、そして文書の上で評価していかねばならない。 |
| ● |
自己評価を伴わない行動は不誠実なものであり、状況は変わりつつある。 |
| (BCSD報告書:「チェンジング・コース」第6章 企業経営の変革より) |
|
3.システム構築から認証取得まで
環境マネジメントシステム(EMS)を構築して審査を受け、認証取得するためには、どのような準備が必要なのでしょうか。一般的な準備の流れを紹介します。
| Step1 準備の準備 |
| トップの号令 |
トップがEMSに関心を持ち、担当者に情報収集を指示する。 |
| 情 報 収 集 |
業界他社の動向、ISO14000sに関する情報を収集し、自社におけるEMSの必要性、メリットなどを調査する。 |
| 計 画 策 定 |
調査結果と認証取得までの大まかなスケジュールと費用等についてトップに報告する。 |
| トップの決断 |
トップが、ISO14001への取り組み・認証取得を決断し、宣言する。キックオフミーティングを開催する。 |
| Step2 構築の準備 |
| 組 織 整 備 |
構築の推進母体(プロジェクトなど)を組織する。 |
| 法規制の取り纏め |
自社に関係する環境法令等の規制について取り纏める。 |
| 初期環境調査 |
製品、サービス、活動などについてプロセス分析を行い、環境側面を把握する。 |
| 環境影響評価 |
環境側面の環境への影響を評価し、最も重要なものを特定する。 |
| Step3 システム構築 |
| 環境方針・目的・目標設定 |
特定された環境影響に基づいて、環境方針・目的・目標を設定する。 |
| 環境管理計画作成 |
設定した環境目的・目標を達成するための環境管理計画を作成する。 |
| 文 書 整 備 |
EMSに必要な、文書を整備、追加する。なるべく既存文書を活用する。 |
| 内部監査の準備 |
内部監査員を養成し、内部監査の手順を確立する。 |
| 測定・記録 |
特定した環境影響について、監視測定するシステムを確立する。 |
| 訓練・教育 |
予想可能な事故、緊急事態に対する訓練等を規定、計画する。 |
| 経営者の見直しの準備 |
トップが、EMSやパフォーマンスを見直す手順を確立する。 |
| Step4 運 用 |
| 実施・運用 |
整備した文書類で、実際にEMSを運用する。 |
| 内 部 監 査 |
内部監査を実施する。監査報告書を作成する。 |
| 経営者の見直し |
トップが、EMSや目的、目標の達成度について見直す。 |
| Step5 認証取得 |
| 申 し 込 み |
審査登録機関に申し込み、本審査までのスケジュールを立てる。 |
| 文 書 審 査 |
文書(マニュアル類)を送付し、チェックを受ける。 |
| 予 備 審 査 |
本審査を受けるレベルに達しているかを確認してもらう。指摘事項は本審査までに改善しておく。 |
| 本 審 査 |
内部監査とマネジメントレビューが済んだ段階で、本審査を受審する。 |
| 認証取得(登録) |
審査登録機関において、第三者がメンバーの判定会にかけられる。合格と認められれば、登録証が発行される。 |
| 維 持 審 査 |
半年もしくは一年ごとに、維持審査(サーベイランス)を受ける。 |
| 更 新 審 査 |
3年ごとに、更新審査を受ける。 |
4.環境マネジメントシステムのメリットは?
(1)システム導入のメリット
組織内に目標管理制度のようなPDCAサイクルが構築され、継続的な改善に向けた活動が図れます。そして、組織内にトップダウンとボトムアップのサイクルが生じ、自主管理体制が整備されます。
その他にも、責任体制の明確化、組織内文書のルール化、組織内外の情報伝達のルール化、考える習慣の育成、危機管理による環境負債の予防があげられます。
ただし、そのためには、従業員一人一人に対する、徹底した教育・訓練の充実が必要です。

(2)第三者認証取得のメリット
環境パスポートの取得、グリーン調達への対応、販路の拡大、企業のイメージアップ等があげられます。
(3)環境目的・目標に設定し取り組んだ結果として得られるメリット
例えば、廃棄物の削減、省資源、省エネルギーなどの「環境コストの削減」のメリットです。実際には、企業が環境負荷低減の目的を設定し、実施した結果、明らかになるものです。また、企業自身が何を目指すか、あるいは最終的にどのレベルまで達成できたかにより、メリットのレベルも大きく違ってきます。
5.経営者にもとめられること
組織が環境マネジメントシステムを導入し、継続的改善を行う場合は、経営者のコミットメント(宣言、約束)が最も重要です。コミットメントは、その企業の最高経営層が継続的改善を誓う第一歩であり、そのレベルによって、システム自体の完成度に大きな格差を生じます。
|
| ● |
導入と継続的改善に必要な財政資源(人、物、資金)の確保 |
| ● |
導入推進チームへの適切なスケジュールのための時間配分 |
| ● |
導入推進チームが必要とする知識取得に向けた教育の実施 |
|
容器包装リサイクル法対応
及び産業廃棄物関係セミナーのご案内
−地球に優しい企業を目指して−
平成7年6月に「容器包装リサイクル法」が制定され、同年12月に対象となる容器包装、対象事業者、市町村と事業者との責任分担等に関する政省令が、平成8年3月には基本方針が制定されました。これにより平成9年4月から、ガラスびん及びペットボトルについて、中小企業者を除く事業者に対して再商品化の義務が課せられました。さらに、平成12年4月からは紙容器以外の「紙」及びペットボトル以外の「プラスチック」も含め、中小企業者にリサイクルの義務が課せられることになります。
このため、スムーズに「容器包装リサイクル法」へ対応できるよう、また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」の改正概要と産業廃棄物を巡る最近の状況等についても、併せて下記の内容で講習会を開催いたします。
| セミナーのテーマ |
講 師 名 |
● 「容器包装リサイクル法」の解説
● 再資源化技術の情報提供 |
ガラスびんリサイクリング推進連合
事務局長 森 雅 博 氏 |
| ● 産業廃棄物関係―「廃掃法」の改正概要及び産業廃棄物を巡る最近の状況 |
(財)クリーンジャパンセンター
相談部長 間 宮 陸 雄 氏 |
| 日 時 |
平成9年11月19日(水) 午後1時30分〜午後4時50分 |
| 場 所 |
シャインプラザ平安閣秋田 TEL 0188-63-1122(代) |
| 参 加 費 |
無料・定員50名(定員になり次第締め切らせて頂きます。) |
| 申込期限 |
平成9年11月17日(月) |
| 主 催 |
中小企業事業団・(財)秋田県中小企業振興公社 中小企業情報センター |
| 後 援 |
秋田県・あきた食品振興プラザ |
| 申込み先 |
秋田県中小企業振興公社 中小企業情報センター |
| 〒 010 秋田市山王6−1−13 山王プレスビル5階 |
| TEL 0188-63-8401 FAX 0188-64-7440 担当鈴木 |
|