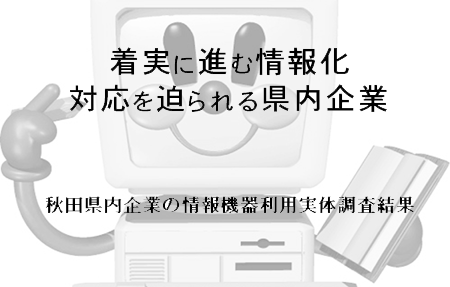|
|
数年前まで馴染みの薄かったインターネットの普及率は既に10数%に達し、電子商取引が急速に占有率を伸ばす等、情報化が全世界規模で進展している。これに対し、県内企業の情報化がどの程度進んでいるのか、また、その隘路や今後の動向について調査を実施した。
本調査は、県内企業の中から2,000社を無作為に抽出し、平成11年10月時点における情報機器の利用状況等を郵送による書面で実施した。このうち349社から有効な回答があり、回収率は17.4%であった。
集計は、表1のように回答企業を製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業の5業種と、従業員数の規模別に分けて行なった。
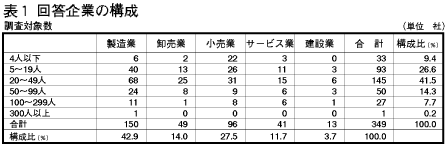
1. 情報機器の利用状況 パソコンの導入率は81.1% 現在一般に利用されている情報機器11種の利用状況を表わしたのが表2である。 昨年と比較して、「パソコン」は7.3ポイントの伸び、特に顕著なのは「デジタルカメラ」で、36.9ポイントの伸びを示した。デジタルカメラの特質上パソコン等何らかの情報機器に接続して使用されることから、情報機器を能動的に使いこなすスキルの上昇が覗え、パソコンブームと共に情報化の進展が急速に進んでいる。 従業員規模では、「オフコン」や「ファームバンキング」では従業員規模が大きくなるに従い保有率が高くなっているが、「パソコン」や「デジタルカメラ」では、企業規模の大小による保有率の格差が縮小されている。 これらの情報機器の使用頻度をみると、コンピュータ関連機器では、回答企業の67.3%が「パソコン」を「頻繁に利用する」と回答し、次いで27.8%の「オフコン」が続いている。 一方、普及率の高い情報機器にもかかわらず「使用しない」とした内容をみると、「端末専用機」78.2%、「オフコン」69.3%、「ファームバンキング」66.8%、「ワープロ専用機」45.8%となっている。 今後導入したい情報機器では、「特にない」とした回答が52.2%と、前回の調査に比べ17ポイント増加、情報化機器の導入が進んでいることを覗わせる。 今後導入したい情報機器と業界の関係をみると、「パソコン」は従業員4名以下と100名以上の企業で導入意欲が高い結果となった。建設業で「デジタルカメラ」と「スキャナー」がそれぞれ30.0%、サービス業で「ファームバンキング」18.2%、「携帯端末機」15.2%と、業界により特徴的な結果を示した。
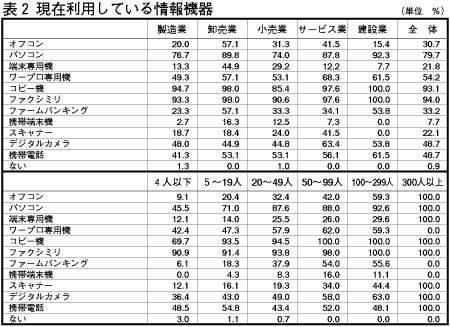
2. コンピュータシステムと利用状況 建設業の46.2%がCADを導入 現在保有のコンピュータシステムと今後導入したいコンピュータシステムを集計したのが表3である。 現在利用しているコンピュータシステムについては、「ERP(統合業務システム)」「POS(販売時点情報管理)」「EOS(オンライン受発注システム)」がいずれも20%台の普及率であった。これらに現れる数字は当然ながら業界による営業形態、管理手法の違いが明確に現れている。 具体的には、製造業では「ERP(統合業務システム)」16.0%、「EOS(オンライン受発注システム)」12.0%で多く、卸売業では「ERP(統合業務システム)」44.9%、「EOS(オンライン受発注システム)」と「POS(販売時点情報管理)」が38.8%。小売業では「POS(販売時点情報管理)」38.5%、「EOS(オンライン受発注システム)」34.4%。サービス業では「ERP(統合業務システム)」36.6%、「POS(販売時点情報管理)」と「POP販売(販売広告作製)」が22.0%。建設業では「CAD(コンピュータ援用設計)」が46.2%と際立っている。 他方「特に使用しているシステムはない」との回答も全体で38.7%あり、従業員規模が小さくなるにつれてこの回答率が高くなっている。 今後導入したいコンピュータシステムについては、「ERP(統合業務システム)」と「EOS(オンライン受発注システム)」と回答した企業が多かった。 業種別では、「ERP(統合業務システム)」を導入したいとするのが建設業で33.3%、小売業20.8%、サービス業16.7%で高い。特に建設業では、案件ごとの複雑な施工管理、実行予算管理をシステム化しようとする動き強い。卸売業で「POS(販売時点情報管理)」と「EOS(オンライン受発注システム)」が12.9%と多い。

3. ネットワークの利用状況 着実に浸透し始めたインターネット コンピュータを利用したネットワークの利用状況をみたのが表4である。 今回の調査で、初めてインターネットと電子メールを項目に入れた。その結果、全業種でコンピュータ単体の利用から、ネットワーク機器としての利用にシフトしつつある。特に「どのネットワークも利用していない」との回答が52.1%と、前回調査比べ17.6ポイントも減少している。 具体的には、「LAN」の利用が全体平均で22.1%、「インターネット」が35.2%、「電子メール」が27.5%となっている。また前回全く利用なしの結果であった「モバイルコンピューティング」が3.4%となり、携帯電話の普及と共にモバイルコンピューティングを利用する企業がしだいに増加する傾向にある。 これらネットワークの使用頻度をみると、「インターネット」の利用が「頻繁に利用している」「時々利用している」を合わせると35.2%、次いで「電子メール」が27.6%、「LAN」が22.1%と、最近の情報通信インフラの整備に伴って、インターネットを中心とした新しい情報通信手段が企業活動にとってもその比重を増してきている様子がみえる。 今後導入したいネットワークでは、「インターネット」で全体平均35.4%、「電子メール」22.9%と、いずれの業界もコンピュータを媒体にした通信ネットワークの導入意欲は高く、これらのネットワークを社内情報共有化等限定的な利用に留まらず、社外へ積極的に情報を発信していこうとする気運の高まりがみられる。
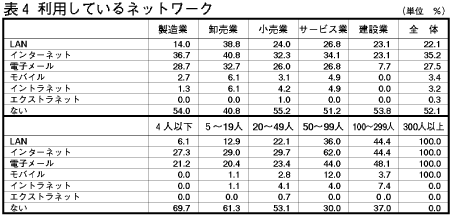
4. コンピュータ処理業務 主力は「給与・会計・財務処理」 現在コンピュータで処理している業務の内容をみたのが表5である。 全ての業種に共通してコンピュータ処理が進んでいる業務は、「給与計算」55.9%、「会計処理」51.9%、「販売管理」50.7%、「財務処理」42.7%。「計画立案」や「市場予測」等、企業の経営戦略に関わる部分での活用は依然として低率にとどまっている。 (製造業) 製造業では、「生産管理」をコンピュータ化しているとした企業が31.3%あり、他の業種と趣を異にしている。今後コンピュータ処理したい業務では、資材管理から生産管理、コスト管理まで製品製造全般に関る部分をコンピュータ処理したいとする企業が多い。これは、余分な在庫を持たず、歩留まりを最大限上げようとする企業の姿勢を反映したものであろう。 (卸売業) 卸売業では、87.8%の企業が「販売管理」にコンピュータを活用しており、次いで「顧客管理」53.1%、「製品・商品管理」38.8%、「統計処理」が30.6%となっている。 今後処理したい業務については、「製品・商品管理」「原価管理」「市場予測」がそれぞれ12.2%と多い。特に「市場予測」については、全業種のなかで一番回答率が高い。 (小売業) 小売業では、「顧客管理」を49.0%の企業が実施しているのは前回と同様だが、「販売管理」が64.6%と前回より一挙に18.5ポイント増加したのが目に付く。 今後については、特に「経営計画立案」にコンピュータを利用したいとする回答が15.6%と前回に比べ7.8ポイント伸びている。これは小売業においてもコンピュータの戦略的機能に企業が目をむけ始めていることを覗わせる結果である。 (サービス業) サービス業では、その業態上「顧客管理」が48.8%と最も多く、次いで「販売管理」の39.0%、「原価管理」31.7%となっており、いずれも大きく伸びている。また、「統計処理」が24.4%と倍増しており、今後コンピュータ処理したい業務の「経営計画立案」14.6%との相関を裏付ける結果となった。 (建設業) 建設業では、「原価管理」をコンピュータ処理している企業が46.2%と多い。これは受注環境が厳しくなり、限られた予算の中で収益を確保するために、予算管理や工事ごとの原価管理を的確に行う必要性から生じた結果である。 今後処理したい業務については、「人事管理」との回答が30.8%に達している他、「原材料・部品管理」「原価管理」「顧客管理」「スケジュール管理」がそれぞれ23.1%と続いている。
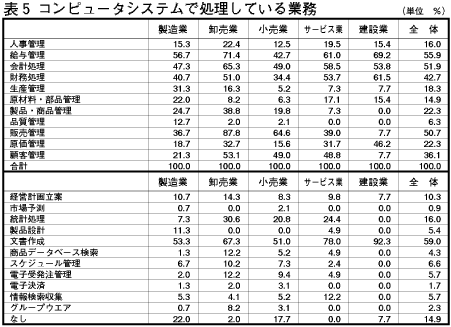
5. ソフトウェアの導入方法 パッケージソフトの比率が更に拡大 現在利用しているソフトウェアの導入方法についてみたのがグラフ1である。 全体の62.5%が「パッケージソフト」を利用しているとしており、「外部に開発を委託」する21.8%を大きく上回っている。業種別でみても、元々「パッケージソフト」利用が進んでいた建設業を除き、全ての業種で「パッケージソフト」利用の割合を大きく伸ばしている。これは、パソコンの性能向上に伴い、より業界ニーズに対応した使いやすいパッケージソフトが開発、提供されるようになったためと考えられる。
6. 現在使用しているパッケージソフト ワープロ・表計算ソフトはスタンダード化 全業種で「ワープロソフト」73.9%、「表計算ソフト」が72.5%と、これらのソフトがスタンダード化し、広く使用されている。また、今回は「財務・販売管理用ソフト」の使用率が57.5%と、一挙に23.6ポイントも増加した。しかし、これは主に社内事務の合理化に利用されているに留まり、「リレーショナルデータベースソフト」(11.8%)「カード型ソフト」(4.3%)といったソフトの利用はなかなか進んでいない。この原因は、社内でそれらのプログラムをシステムとして構築できる人材が不足していることが背景にあると思われる。
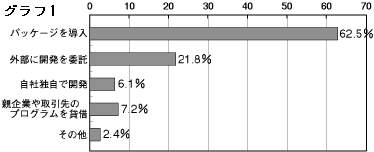
7. 情報化を進めていく上での課題 誰でも使えるシステムに 情報化を進めていく上での課題をみたのがグラフ2である。 「限られた者しか操作できない」との回答が55.1%で、前回に比べ倍増している。この傾向はどの業種にも共通しており、情報の共有化がなかなか進まない大きな要因になっているばかりでなく、企業の危機管理上も好ましくない。以下「調整変更が難しい」30.8%、「情報化に投資する余裕がない」26.4%の順となっている。 情報化を進めるプロセスにおいて重要なのは、社員の意識改革とシステムに対する知識の向上である。 それに平行して、マニュアルに頼ることなく誰でも操作できるようなソフトの開発も望まれるところである。
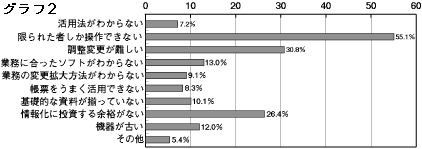
8. 自社の情報化レベル 4割が情報化の遅れを認識 自社の情報化レベルをみたのがグラフ3である。 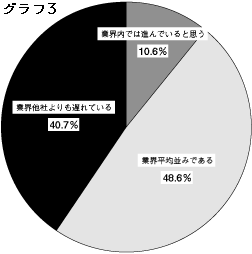 「業界内では進んでいると思う」と回答した企業は全体の10.6%に過ぎないが、前回に比べて2ポイント強増加、「他社より遅れている」とした回答が40.7%で、他社をみて情報化の必要性を再認識している様子が覗える。 「業界内では進んでいると思う」と回答した企業は全体の10.6%に過ぎないが、前回に比べて2ポイント強増加、「他社より遅れている」とした回答が40.7%で、他社をみて情報化の必要性を再認識している様子が覗える。業種別にみると、卸売業とサービス業で「業界の平均並みである」と「業界内では進んでいる」とする割合が68〜70%台と高く、逆に建設業では、「業界他社より遅れている」とする企業が61.5%あり、情報ネットワークの活用が他の業種に比べ遅れているとの認識があるようだ。
9. 情報化を担当する人材の確保 人材は日常業務のなかで育成 「日常の仕事の中で育成」とする回答が全体の76.5%を占め、「社内研修」が16.3%で続いている一方で、「人材確保に苦慮している」との回答が13.7%、「新規に社員を採用」が3.3%であった。 情報化担当者の多くは既存業務の傍ら情報化業務も担わなければならないのが現状のようである。
10. 情報化の捉え方 情報化は「極めて重要」 情報化の捉え方をみたのがグラフ4である。 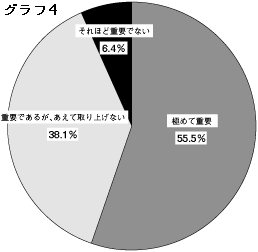 情報化が企業の経営戦略上「極めて重要」との回答が全体の55.5%で、前回比5.2ポイント増加。「それほど重要ではない」とする回答は6.4%に留まっている。 情報化が企業の経営戦略上「極めて重要」との回答が全体の55.5%で、前回比5.2ポイント増加。「それほど重要ではない」とする回答は6.4%に留まっている。業種別では、卸売業、小売業、サービス業で「極めて重要」と認識する企業が全体平均を上回っている。これは特に流通やサービスといった極めて多様化したニーズへの対応を求められる企業にとって、情報化が強い武器になるとの認識の表れと考えられる。しかし、これらの業種に留まらず、他の業種にとっても情報化の戦略的優先順位が高くなる傾向は同じである。
ここ数年の情報通信インフラの整備は、携帯電話やインターネットをはじめとする情報化の進展を劇的に進めた。このように社会のあらゆる場面で情報機器によるネットワーク化が進展すると、企業にとってもそれへの対応を余儀なくされるばかりでなく、企業活動のあり方そのものに影響を与えると言っても過言ではない。 その意味で、県内企業は事務処理効率化中心のコンピュータ利用から、情報ネットワーク機器としての活用という新たな段階を迎えている。 注目されるのは、情報化の進展は企業の規模による情報収集、情報発進能力の格差を縮小する傾向にあり、しかも地域的な要素も問題にならず、小規模企業にとっては大きな飛躍の可能性を与えられたことになる。 一方で、県内企業にとって「情報化」にかかるコストと経済効果、情報化を担う人材確保に苦悩する現実も少なからずあるのも事実。 当中小企業情報センターは、この調査結果を業務に活かし、県内企業が「情報化」をスムーズに進め、全国規模の企業活動を展開する企業が現れるよう、一丸となって支援して行きたいと考えております。 最後に、本調査にご協力いただきました企業の皆様に厚く御礼申し上げます。
|