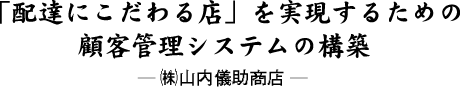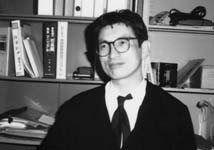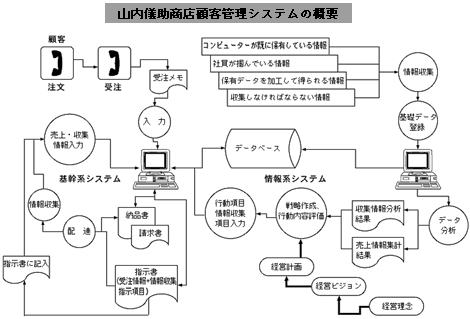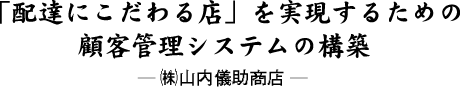
当中小企業情報センターでは、情報化による経営革新を目指す企業に対して、継続的にアドバイザーを派遣して情報化を支援する「情報化モデル企業育成事業」を平成8年度より実施してきた。このモデル企業の事例を通して、多くの企業の皆様に情報化について少しでも理解を深めてもらおうというのが本事業の目的である。
今月と来月にわたり、昨年度のモデル企業2社の指導事例を紹介していく。
|
湯沢市で米やプロパンガス、灯油、肥料等の販売と米穀集荷等を営む(株)山内儀助商店は、明治29年創業の老舗。当店は、これらの商品を電話注文により日配しているが、大資本による小売業の独占化傾向が強まる中,地場の小規模店として「配達にこだわる店」を指向している。 |
企業の概要
|
企業名 |
株式会社 山内儀助商店 | |
所在位地 |
湯沢市田町2−4−40 | |
代表者 |
山内 雄司 | |
創業 |
明治29年6月 | |
事業内容 |
米、灯油、プロパンガス、肥料・農薬などの配達による販売、及び米穀の集荷 | |
資本金 |
1,000万円 | |
売上高 |
3億8,000万円 | |
従業員 |
17名 | |
モデル企業育成アドバイザー | |
グループCFG 代表 北澤 正一郎 氏 |
|
■業界の動向
米の小売店は、平成7年11月の新食糧法施行にともない免許制から登録制になり、小売業者数は著しく増加している。経済企画庁が行った物価モニター意識調査結果によると、平成8年8月に行った同じ調査で36%を占有していた米専門店での米の購入割合が、10年3月では23%に低下、一方、スーパーは7ポイント増加し29%でトップに立っている。このため米小売専門店の廃業が相次いでいる。
また、灯油の販売では、石油業界再編の煽りを受けて価格競争は激しく、ガソリンと同じように競合先は多い。さらに、プロパンガスにおいては、通産省による保安基準が厳しくなり、このための設備投資が必要となっているのに加えて、内外価格差への指摘や電気など他のエネルギー需要割合が伸びていることもあり、価格は下がる寸前の状態で、既に値下げを踏み切ったところも出てきている。
肥料においても、減反などで需要が減っている中、外国からの参入もあるなど、当社が扱っているどの商品も厳しさが増している。
■指導依頼事項
そうした中当社では、顧客情報を現場活動に有効・迅速に活かすことが生き残りの道と捉え、当社の約3,000軒の顧客情報を有効活用するための指導を受けたいとの事であった。
そこで、東京都で経営情報システム構築のコンサルティングを行っている、グループCFG代表北澤正一郎氏をアドバイザーに委嘱し、延べ10回の派遣指導を行った。
■現状の情報システム
当社は1984年より会計機、1989年よりパソコンを導入、1996年にはLANを構築(現在Windows NT活用)し、社長自らがコンピュータを操作し、情報化に意欲的に取り組んできている。
現状はパソコン7台、プリンタ2台、バーコードリーダー2台を導入し、灯油とプロパンガス部門では業界設備メーカーが開発した販売管理パッケージソフト、米穀と肥料部門では市販パッケージソフト(PCA)を利用して事務処理を行っている。
この他、仕入・買掛管理システム、財務会計システム、ワープロや表計算ソフトも活用している。
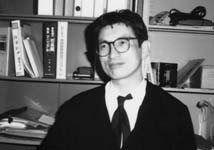
山内 雄司 社長
■経営課題
情報化指導を進めるに当たり、当社の抱えている経営課題を北澤氏に整理してもらった。
(1)「配達にこだわる店づくり」の具体的な行動がなされていない
当社では、「配達にこだわる店づくり」を掲げているが、今まで具体的な行動はほとんど行われていない。
(2)顧客情報が一元的に管理されていない
プロパンガスと灯油をLPG管理システムで、米と肥料を販売管理パッケージソフト「PCA商魂」で管理しているため、同一の顧客を二つのシステムで管理している。そのため、場合によっては同じ顧客にそれぞれの部門で訪問することがある。
(3)経営理念が明確でない
仕事を効率的に行うということだけでは「配達にこだわる店」を作ることができないのだが、「当社はこういうものやサービスを商品にする」「こういうことで地元の社会生活に貢献する」というこだわりが、明確になっていない。このため、社員の行動ベクトルが一致していない。

■改善案
これらの、課題を解決するため、当社では次の事項を実施する事にした。
(1)経営理念と行動規範の作成
「お客様のために当社は何をする企業なのか」 を明らかにさせ、社員に周知するため「わが社の経営理念」と「わが社の行動規範」を下記のように定めた。
・世のため人のために貢献する
・無駄を除き、よく働き、ベクトルをあわせ、正々堂々儲ける
・全員参加の経営を通じ社員の成長と物心両面の幸せを求める |
・最善の訪問サービスをすること
・最善を尽くし、最速を指向すること
・相手の立場になり、考え行動し詳細にこだわり心を配ること |

(2)顧客データ・ベースを整理する
顧客情報を有効に活用するための前提として、処理や管理を商品単位ではなく、お客様単位に変更する必要があることから、次の事項を実施する事にした。
1.顧客管理項目を整理する
お客様のための企業になるためには何よりもお客様のことをよく把握する必要がある。
そこで、まずお客様に関するデータベースを作成することとし、そのために収集すべきデータ項目を洗い出した。「お客様に関するどのような項目があれば良いのか」を検討し、「住所」「氏名」など、最終的に100を超える項目が出された。
収集方法は、(1)既に収集しコンピュータの中に入っている(2)各担当者の頭の中に入っている(3)改めてお客様より収集する(4)調査・分析して得る、の4パターンに分けて収集することにした
2.顧客データを統合
現在稼動しているシステムは前述のように大きく分けて2つあり、また、各々のフォーマットも異なっている。
そこで、各システムが持っている顧客データや売上情報を一旦表計算ソフトのExcelデータに移し、更にそれをリレーショナル・データ・ベースソフト(RDB)のAccessを利用した顧客データベースで管理することにした。
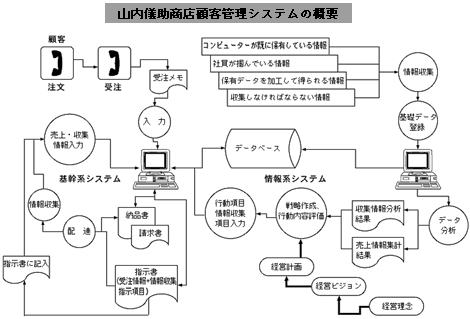
(3)配達にこだわる店を実現するための仕組み
顧客データベースの活用を含めて「こだわりの店」を実現するため、「日々何をどのように行うべきなのか」その仕組みを確立する事が必要である。
そこで、下記のような1.〜3.の行動の積み重ねを毎日行うことにした。
1.顧客データベースから、訪問するお客様に関係のある指示(情報)を打ち出す
2.各担当者はその指示に従って行動する(配達、集金、クレーム処理、データの収集など)
3.収集したデータを、顧客データベースに入力する
「指示書」は配達や集金など全ての作業に際して発行するが、その書類の様式は当面一種類のみとし、取り扱う内容も欲張らず実現可能な25の項目に範囲を絞ることにした。
現在、今回の指導のもとに一日も早いシステムの稼働をめざし、システムの開発に取り組んでいる。

|
□アドバイザーの意見
当社の指導に対して、北澤アドバイザーは次のように指摘している。
戦略的な情報化がなかなか実現できない大きな理由の一つに、「明確な経営理念がない」ことが掲げられる。
「事務処理レベルの情報化」の場合はそれほどではないが、戦略的とも言える「お客様のための情報化」を実現する場合、「当社はどんなことで地域社会に貢献するのか」を明確にし、この事を運用の主役になる社員が納得していなければ「顧客情報を活用しよう」「情報化をすすめたい」と取り組んでもまず駄目である。
当社も当初この状態であった。
コンピュータを利用した期間は長く、情報機器は整備されているし、社長自身いくつかの情報技術を身につけてもいる。だが、結果的に見ると企業のあるべき姿をふまえた全社的な戦略的な展開ではなく、部分的な積み重ねで終始していたと言える。基本的なレベルの情報化ならこれでも構わなかった。
しかし、経営環境が厳しくなり「このままではいけない」ということで「配達にこだわる店作り」を目指し、その手段として顧客情報の活用を取り上げたのはよいが、いざ取り組んでみると顧客台帳が不備であるため、活用のためにはあらためてお客様に関するデータを収集する必要がある、また、部門毎にシステムが作られているので顧客台帳の一元化にも取り組まなければならないという状態であった。
今回実現を目指している「お客様のための情報化」はとても大きな効果が見込めるし、取り扱う量でなく質で勝負できる中小企業に適したシステムだと思う。
反面、中途半端な考えや対応ではかえって信用を失い、企業の存在に影響が出てくる可能性のある情報化である。厳しいことを求めるようであるが、お客様に当社の思いが伝わるようになるまでに行うことは、それこそ山ほどある。顧客に関するシステムがいくら立派にできても、その運用や普段の行動も厳しくチェックされる。
情報化のモデルとしてしばしば取り上げられる「セブンイレブン」でも「このようなお客様がこの商品を買った」までしか分からないのに、当社はお客様のところにその都度訪問するので「誰が何を買ったのか」まで分かる。この「訪問する」という強みを生かし、上手に「顧客データベース」を運用すれば「配達にこだわる店」を作ることができ、労働集約的な企業から一味も二味も違う企業に変身できる。このためには、社員は常にお客様からの発想を持ち、「良き社会人」「良き企業人」となる必要がある。
|
|