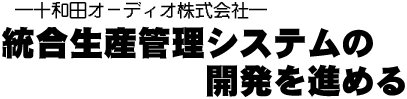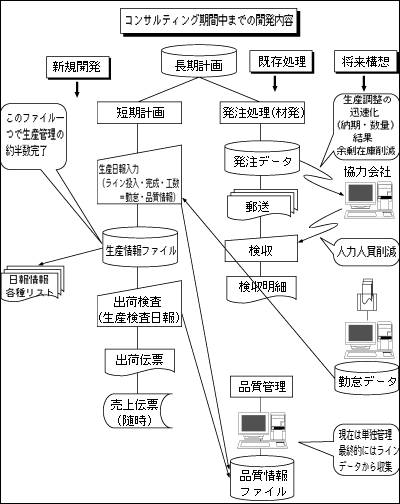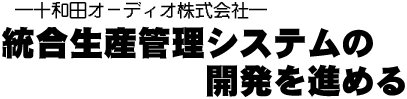
平成10年度に実施した情報化モデル企業育成事業指導事例を紹介する2回目。低コスト、短納期化に対応するために、資材の調達先と協力会社等と連携を取りながら統合生産管理システムの構築を進めている十和田オーディオ(株)の事例を紹介する

小坂町で高級ラジオやCCDカメラ等を生産する十和田オーディオ(株)は、従業員数500名、売上高189億円、国内4事業所、協力会社県内2社、国外(中国)1社を擁しグループ総売上高が300億円に達する秋田県を代表する電気機器メーカーである。
企業の概要
|
企業名称 |
十和田オーディオ株式会社 | |
所 在 地 |
秋田県鹿角郡小坂町小坂字大稲坪98番地 | |
代表者名 |
伊藤 忠夫 | |
創 業 |
昭和49年7月 | |
事業概要 |
通信機器の設計及び製造(ラジオ、トランシーバー、CCDカメラ等の製造) | |
資 本 金 |
2,000万円 | |
売 上 高 |
189億円 (1997年度) | |
従業員数 |
500名 | |
モデル企業育成アドバイザー | | 畠山 有正 氏 |
|
■業界の動向
電気機器業界は、電子部品、家庭電気機器部品、音響機器などその内容は多岐に渡るが、東南アジア諸国の台頭、低迷する国内需要、急速に進む技術革新など非常に変化が激しく、また常に国際競争にさらされている業界である。
こうした中で業界各社は、生産工程の自動化や合理化を図るとともに、コンピュータシステムによって生産管理を統合して大幅なコスト削減と納期短縮を図りたいとする企業が多い。
■指導依頼事項
これまで当社は、主要得意先のソニー(株)が開発した生産管理システムを使用して在庫管理や生産計画の立案等を行ってきた。しかし、システムの対象業務が限られており、システムに貯えられているデータも有効に活用されないままでいた。
当社では、これまで手作業で集計・管理してきた生産実績データや品質管理データ、出荷データを、タイムリーに処理するコンピュータシステムを構築することによって、納期の短縮や在庫の削減、間接部門の人員削減を進め、更には、それらのデータを会計処理に連動させて、日次決算まで行いたいと考えていた。
そこで、当情報センターでは既に自社の統合管理システムを構築している畠山有正 氏をアドバイザーに委嘱し、延べ10回に渡る指導を行った。

主力の製品
■現状の情報システム
当社では、平成2年にソニーが開発した工場管理システム(SPICS)を導入して資材の発注業務を、平成9年には同じくソニーが開発した生産管理システム(PROCS)を導入して生産計画の立案等を行ってきた。
また、社内にプログラマー5名を擁してこれらシステムの変更や修正・拡張を行うと共に、給与計算システム等を開発してきた。更に、各部署にはパソコンを導入し、表計算ソフトなどを利用して管理資料を作成してきた。
■情報システムの課題
指導を進めるに当たり、当社の情報システムの課題を整理した。
(1)高性能のハードを揃えているが、有効に活用していない
ハードの容量が不足しているとの事だったが、ファイルのレイアウトや実データの容量等を確認したところ、使用していないシステムやファイルが多数あり、それらが多くの領域を取っている事が分かった。これは、システムのインストール時に予想されるデータ量の領域を確保したものの、その後メンテナンスしていないために起こった問題であろう。
(2)システム全体を正しく把握していない
SPICSやPROCSのファイルレイアウトを見ると、当社が実施したいとしている業務のプログラムがかなり含まれている。提供されたシステムのためかシステム全体を正しく把握・検証している者がいない。
(3)手作業が多い
各部署が使用しているパソコンとPROCSデータとの連携が出来ていないため、PROCSの出力データをパソコンに再入力している。また、パソコンで集計する帳票が多く、パソコンに再入力する作業が非常に多い。
主要材料の発注業務はSPICSで行っているが、内職向けの発注などは手作業で処理しており手作業とコンピュータ処理が混在している。
(4)集めた情報が関連部署に伝わっていない
コンピュータ化によって解決したいとする事項は多いものの、必要情報の収集に手間取っていたり、集めた情報が関連する部署に伝わっていない。
■改善案
畠山氏はこれらの課題について、次のようにアドバイスした。
(1)システム全体に関するこ
・取引先や仕事の内容が変わると、それに併せてプログラムの修正が必要になる。当社においては5名のプログラマーを擁している事から、自社によるシステム開発が望ましい。
・データの収集は「継続」「確実」が基本で、中途半端なデータは判断ミスの原因になる。また、収集したデータは確実に利用し、結果は何らかの方法で作業者にフィードバックすることが必要である。
(2)生産日報の集計
長期計画を短期計画に落とし込んだ短期計画用のファイル (生産日報等の実績データ等を集計するファイル)を作り、これまでパソコンで行ってきた生産日報の集計や勤怠・品質管理等の管理資料の作成をシステムの中に組み込む。
(3) 出荷検査
これまでは出荷検査結果を手作業で処理していたため、データの入力や伝票発行が後手に回り、売上結果が出るまでにかなり時間がかかった。今後は、出荷製品の検査結果が端末に入力されると売上が計上するようにする。
(4) 品質管理
ラジオなどは最終商品なことから、市場からのクレームに備えて、ロット管理はもちろんのこと、製作過程での情報を適時検索できるシステムにしておく事が必要である。また、増え続ける品質管理資料を整理統合し、資料の電子データ化を進める。
(5)勤怠管理
データ取りこみはパッケージソフトを利用し、運用ソフトは自社開発する。データは勤怠管理(給与計算等)に使用することは無論のこと、生産日報の集計や原価管理などにも利用する。
(6)協力会社とのオンライン化
協力会社とのオンライン化は、手間がかかるようではあるが、短納期化への対応や納期・数量等の変更、検収処理の迅速化・省人化、さらには過剰在庫の圧縮などその波及効果は大きい。通信設備が整っていることから、今後は協力会社への指導を進めながら発注・検収データのオンライン化を進める。
(7)財務管理ソフトの開発
上記システムの開発によって売上、買掛の管理が可能になる事から、これらの毎月のデータを集計する財務用ファイルを新たに作成し、そのファイルに、その他の買掛データ(電気代・図書費・交際費・燃料費・事務用品費他)や、減価償却費を反映させる事によって月次の損益がわかるようになり、また、経理上の製造原価も割り出せる。
(8)オフコンサーバーからパソコンサーバーに切り替える
機器の導入コスト、マルチメディアへの対応、通信の容易性等から考えて、現在オフコンサーバーを核としたLANをパソコンサーバーに切り替えていくのが望ましい。
しかし、パソコンでシステム開発ができる人材が少ないことから、会社としてパソコンに切り替えることを宣言し、パソコンによる開発者を早期に養成することが重要である。
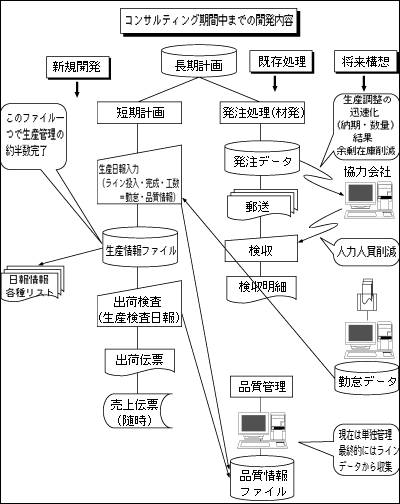
■指導後の状況
当社では、プログラミングの一部を外部に委託したが、今回の指導に沿って社内でシステム開発を進めてきた。
現在、生産日報の集計については40数ラインの全ラインに展開、品質管理システムも既に完成しており、出荷管理システムはテスト中である。また、仕入先・外注先とのオンライン化については、現在関連企業1社とテストを行っている段階で、これが旨く行けば主要調達先10社に横展開していく方針である。
当初西暦2000年問題等の対応に追われたため開発は遅れ気味であったが、数本のシステムが実際に動くようになり加速度的に開発は進んでいるようである。システムの開発を担当してきた小林愛子企画課長は「まだまだ予定より遅れていますが、やっと目途がつきました。これからは財務や原価計算まで持っていきたいです」としている。

システム開発担当している小林課長(左)と伊藤さん
|
■アドバイザーの意見■
製造業では製造品目の違いはあっても、受注して納品する基本形態はどこも同じである。また、その間に発生する仕入・支払・請求・生産・品管・在庫・工数・原価・賃金等も同様である。従って、生産管理や原価管理を行おうとした場合、入力画面や出力帳票の書式の違いはあっても、システムの全体構成は他社でも十分に活用できる。
ただし、全体の構成は同じであっても、内容は得意先や取引形態によって変化する場合が多々あるので、プログラム自体は常にヴァージョン・アップ出来る体制が必要である。更に、システム自体は人間が使用するものであるから、使いやすい事はもちろんだが、使う人の教育が重要な事はいうまでもない。
しかし残念な事にこれが出来ていなくて、システムがうまく稼動していない例が多い。システム開発を始める前に人質管理を再構築する必要がある。
「情報システムに完全は無い」ので、システムが業務の流れに乗っているのかどうかを常に確認し、「気が付いたらシステムが会社の業務を停滞させていた」と言う事が無いように気を付けて欲しい。
|
|