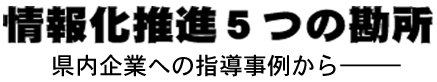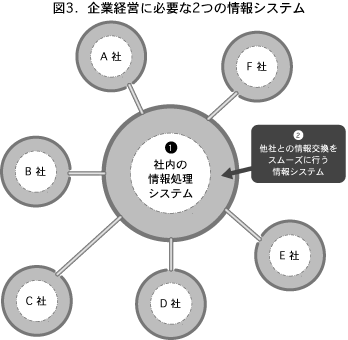急激な情報技術の進展、インターネットによる商取引の拡大、コンピュータの西暦2000年問題などなど、企業の情報化を巡る環境がここ2〜3年の間に大きく変化しています。当情報センターでは、県内企業の情報化を支援する事業を実施しておりますが、最近その中で感じることは、企業間の情報化格差が拡大していることです。
パソコンLANやインターネットを効率的に活用して成功を納めている企業と、未だにコンピュータシステムを使いこなせないためにビジネスチャンスを逃している企業との格差です。この格差が生じる最大の要因は、「情報化に対する経営者の基本的なスタンスの違い、情報化の捉え方の違い」にあるようです。
そこで今月は、情報化を上手に進めて業績を伸ばすための「5つの勘所」を、県内企業の事例を交えながら述べてみます。

「情報」とは?、「情報化」とは?一体どう言うことを意味するのでしょうか。簡単に答えられそうで、答えられないのがこの問いです。
企業の情報化を論じる場合、まず、「情報とは何か」そして「情報化とは何か」を明確にしておく必要があります。経営者の中には、「我が社の情報化は他社より10年は遅れている」と話す方がおられますが、経営者が意味する情報化と社員が捉える情報化を一致させておかないと、判断基準が曖昧になってしまい効率的に情報化を進められません。
当情報センターの情報化アドバイザーの北澤正一郎氏は、「情報」と「情報化」を次のように捉えておられます。「情報とは=自分や企業にとって役に立つメッセージである」、そして、「情報化とは=個人や企業の目的達成のために、情報を効率的に集めて、効果的に活用していく事である」と。諸説はありましょうが、北澤氏のこの捉え方は非常に分かり易く、また、企業の実態に即した理にかなった考え方であると私も同意しています。
その1
情報化をこのように捉えますと、情報化とは単にコンピュータシステムを導入することではないことが分ります。パソコンやインターネットは、あくまでも情報化を効率的に進めるための道具です。情報化を進めるには、これらを導入する前に、目的を明確にしなければなりません。
コンピュータ等を有効に活用して上手に情報化を進めている企業の共通点は、「情報化の目的を明確にしている」ことです。
【A酒造のケース】
“あるべき姿”を示しスムーズに情報化を進める
A酒造はコンピュータの西暦2000年問題への対応を考え、新たな販売管理システムを導入したいとして、当センターに指導を依頼してきました。
当初A酒造の担当者は、新たに導入するシステムは現在使用している販売管理システムのヴァージョン・アップ程度と考えていたようですが、各部門の担当者や部課長の意見を聞くうちに、色々な機能が要求されてシステムが大きくなり、再構築する目的がボヤケてしまいました。
そこで、当社にとってどんなシステムが必要なのかを役員を含めて話しあってもらい、当社のあるべき販売管理の処理プロセスを具体的に示してもらいました。
その結果、システムを構築する目的が明確になり、部課長や社員のベクトルが一致し、部署間の協力体制が出来上がり、システム開発がスムーズに進むようになりました。当社はこの販売管理システムの成功をきっかけに、今では生産管理や在庫管理などもコンピュータで処理しています。 |
その2
コンピュータを導入して情報化を進めようとしている企業担当者に、私はよく「コンピュータに関する仕事は2割、残りの8割はコンピュータ以外の仕事ですよ」と話します。
図1は、コンピュータを活用した場合の、企業の情報処理サイクルを示したものですが、このサイクルの中でコンピュータに関する部分は、データを入力しそのデータをコンピュータが蓄積・加工・分析し、情報を出力するプロセスです。残りの部分の処理、すなわち、出力した情報を基に、判断し、実行(営業や生産活動)し、そこで発生する情報を収集、記録するプロセスは人手によるものです。ですから、いくらコンピュータを導入しても、人手にかかるプロセスの効率を上げない限り一連のサイクルは効率的にならないのです。
しかし、この「人手にかかるプロセス」の構築は、コンピュータのシステムを開発するようにはいきません。コンピュータが出力した情報から担当者が判断を下して、迅速に行動に移せる仕組みを作り上げるには、決裁のあり方や役割分担を見直したり、組織を変えることも必要になるからです。
プログラムの開発はソフトハウスに任せれば済みますが、人手のプロセスは自分達で改善していかなければなりません。ですから、新たな情報システムを開発する場合は、コンピュータシステムの開発にかかる時間以上に、人手のプロセスの改善に時間が割かれるのです。また、システムに慣れる時間も必要です。私の経験では、コンピュータシステムの開発に着手して、システムを使いこなせるようになるまでには最低でも1年は必要です。

その3
さて、コンピュータシステムを構築・再構築する時に苦労するのが、マスタ・データの整理や旧システムから新システムへの蓄積データの移行です。マスタ・データとは、取り扱い商品や仕入先、顧客、社員などの日常頻繁に使用する基礎データを指しますが、これらの基礎データを整理していない企業がとても多いのです。マスタ・データの収集、整理には時間を要するため、システム開発の際に遅れを引き起こす原因にもなっています。
また、コンピュータを利用しているとはいっても、マスタ・データを一元的に管理していない企業も多く見られます。
さらに、マスタ・データが揃わないために、一部を手作業で処理している企業もありますが、コンピュータによる処理と手作業による処理が混在すると、最終の取り纏めの処理は手作業で行わなければなりません。そのため、処理はだんだんと手作業に移行していき、結局はコンピュータシステムが使われなくなってしまう、そんなケースが多いようです。ですから、コンピュータを導入する場合は、あらかじめマスタ・データをキチンと整理しておき、システムを完全な状態に近づけて運用を開始することが肝要です。
【通信販売B社のケース】
顧客マスタ整備しDMのヒット率を向上
食品の展示会等での出張販売と通信販売を行っている県北のB社は、これまで市販の販売管理ソフトによって売上管理(請求書の発行、入金管理等)を、また、年賀状作成ソフトによって顧客管理(DM発行等)を行って来ました。顧客情報を二つのシステムで管理しているため、DMを発行する場合はそれぞれのシステムから対象となる顧客を抽出し、それらの顧客を手作業で照合・抽出(抽出基準は担当者の記憶に任せられてきた)しなければなりませんでした。担当者にとっては、この作業は手間のかかる大変な作業だったそうです。そこで、当センターにアドバイスを求めてきました。
私は、「売上管理と顧客管理を連動した新しいシステムが必要です。そのためには、一本化した顧客マスタが不可欠なので、早急に顧客マスタを整理して下さい」とアドバイスしました。それぞれのシステムが管理していた顧客件数を合計すると約8000件にも達し、これら1件1件を見直し整理する作業は非常に大変な作業だったようですが、約1月をかけて顧客データを整理してもらいました。8000件ほどあった顧客データは約6000件に整理されました。
新たに開発したシステムによって、この6000件の中から対象となる顧客を抽出しDMを実施したところ、なんとヒット率が20%近くの効果的なDMを打つ事がでるようになりました。
どうやら、顧客データ整理の苦労が報われたようです。 |

【建具メーカーC社のケース】
商品マスタの整理にとまどり開発遅れる
建具を生産しているC木工は、西暦2000年問題に対応するために、新たな受注・売上管理システムを開発することにしました。当社は、7年前に数千万円をかけて現在のシステムを開発したのですが、商品の特定に時間がかかることや日次の売上確定処理に問題があったこと等から、今では請求書の発行にしか使われていませんでした。た。
そこで今回は、前回の失敗を繰り返さないように、まずはコンピュータ化できるところからシステム化し、それをヴァージョン・アップする方法でシステムを構築していくことにしました。
しかし、開発を進めていくと商品コードの設計に戸惑ってしまい、開発が止まってしまいました。建具は名称、用途、材質、サイズ、顧客のセット名等の組み合わせによって決まるため、商品を特定するには多くの項目を決めなければならず、それらをどう組み合わせて商品コードを付ければよいのか迷ってしまったのです。結局、商品マスタの整理に3カ月を要してしまいました。西暦2000年を目前に控え、3ヵ月の遅れは大きな損失です。 |
その4
コンピュータシステムを構築する場合は、システムには(1)基幹系システムと(2)情報系システムがあることを理解しておくことが必要です。これを理解しておかないと、システム開発に多くの時間や費用がかかるだけでなく、コンピュータを操作する担当者が使いにくいシステムになってしまう恐れがあります。
【基幹系システム】
基幹系システムとは、営業担当や受注担当者が日常の業務の中で利用するシステムです。お客様からの注文を受けて、納品伝票や発注書、請求書等を出力するシステムです。これは、毎日発生するデータを処理するシステムですから、正確さとスピードが要求されます。また、操作性もポイントになります。データ量は大量になりますし、取引きデータですから、機密やバック・アップを重視する必要があります。
【情報系システム】
これに対して、情報系システムは基幹系システムで蓄えた情報を加工分析して、管理資料や予測資料等の経営資料を作成するシステムです。システムの利用者は経営者や管理職が中心になります。また、週単位や月単位で使用される場合が多く、システムが蓄積したデータをグラフにしたり統計分析する等して、より分かりやすく多面的に見れるようにすることが必要です。

こうしたことから、現場の担当者は基幹系システムの充実を求め、経営者や管理職は情報系システムの充実を求めます。しかし、これらを一緒に開発しようとすると、システム開発に多くの時間と費用がかかってしまいます。情報系システムは基幹系システムの上に成り立つシステムですから、しっかりとした基幹系システムを構築することが先決です。経営者は経営を判断するための情報が欲しいものですから、帳票や画面など多くの管理資料を求めます。しかし、そうなるとシステムは大きくなり開発期間は延びてしまい、肝心の基幹系システムの完成が遅れてしまいます。
今では、基幹系システムが蓄えた情報を表計算ソフトやRDB(リレーショナル・データ・ベース)ソフトで加工できるシステムが一般的になっていますから、情報系システムと基幹系システムを切り離して構築した方が費用の面でも安く上がる場合が多いようです。
【D小売店のケース】
経営者がRDBで顧客データを一元化
県南で米やプロパンガスを販売しているD社は、プロパンガス専用の販売管理システムと市販の販売管理システムの二つのシステムを利用しています。当社もB社と同じように、二つのシステムで管理しているため、同一顧客の売上情報等を一元的に管理できないでいました。
幸いなことに、各システムとも蓄積したデータをテキスト・データに変換できることが分かりました。そこで、顧客別の売上情報を一元的に管理するために、社長自らが各システムの蓄積データをテキスト・データに変換し、アクセスという市販のRDBで顧客情報を一元的に管理するシステムを開発しました。
基幹系の処理には市販のパッケージプログラムを活用し、情報系の処理には社長自らが開発したシステムを活用しているのです。 |
その5
県内企業においても、多くの企業がEOS(電子発注システム)やインターネット等を使って、受発注データや図面データの交換を行うようになりましたが、昨年あたりから頻繁に使われる言葉に、「サプライ・チェーン・マネジメント:SCM」があります。これは、小売→卸・輸送→製造までの一連の工程を効率よく管理して、納品リードタイムの短縮や適正在庫数量の確保に企業が連携して取り組もうというものです。
これを実現するための第一歩が、企業間の情報の共有・交換システムの確立です。小売で得られた購買情報を、シームレスに卸やメーカーに伝えたり、各社が抱えている在庫情報を迅速に把握できる仕組みです。
受発注取引きでは、「発注伝票」は「発注ファイル」に、「納品伝票」は「納品ファイル」に替えて、電子ファイルとして情報を受け渡し、再入力することなく各企業が情報を活用していくことです。再入力はミスの原因となり無駄な作業と時間を使うことになります。常に変化する顧客ニーズに対応して最適な在庫を確保するには、途切れること無く情報交換できる体制が必要です。
このためには、企業には図3に示した様な(1)社内の情報処理システムと(2)他社と情報交換をスムーズに行えるシステムを確立する必要があります。インターネット等を活用して取引先やお客様から情報をスムーズに取り入れ、それを瞬時に社内の指示情報や管理情報に変換して活用する。そして、取引先やお客様の要望する形に情報を加工して提供する。そんな体制が、企業の情報処理システムに求められています。アメーバーの様にお客様の要求に応える仕組みと、その中の「核」となる社内の仕組みが必要なのです。
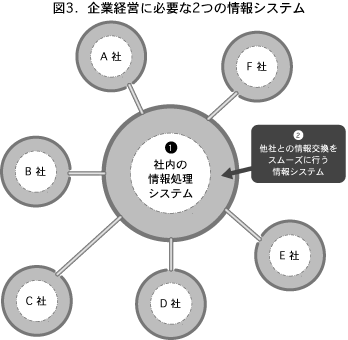
|