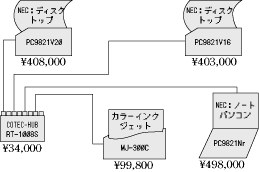| 我が社の情報化戦略 -情報化モデル企業育成事業指導事例より- |
|
県内企業の情報化投資は、バブル経済崩壊後だいぶ押さえられてきたが、パソコンの低価格化やインターネットの普及、西暦2000年問題への対応等が引き金になり、ここ1〜2年積極的な情報化投資が目立つようになって来た。最近の情報化の特徴は、パソコンLANやパソコン通信等のオンライン技術を活用して、これまでの仕事の仕方を大幅に見直し、全社的に情報化を進めようとする点である。 昨年、当中小企業情報センターでは、情報化によって経営革新を図ろうとしている企業に対して、継続的にアドバイザーを派遣し情報化を支援する「情報化モデル企業育成事業」を実施した。今回は、この事業をきっかけに積極的に情報化を進めている2社を紹介する。
プロジェクトチーム編成し
大きなテーブルを囲み、一つの帳票をめぐって活発な意見が交換されている。「この表は本当に必要なの?、別な表にも同じ項目があるじゃない」「そのデータは壜詰製品部で入力すべきですよ」と言った具合だ。
厳しさ増す清酒業界

全社的な経営課題
経営課題に対する改善案
 プロジェクトチームの検討風景
情報化に関する問題点
情報化に関する改善案
|
| 第3ステップ (あるべき姿:2年以内) 社内外とのネットワークによる処理 (ネットワークを活用する情報化) |
| 第2ステップ (1年以内) 媒体を使用した部門間のネットワークによる処理 (フロッピーによるデータ・情報のやりとり) |
| 第1ステップ (直ちに実現すべき姿:6月以内) 情報機器(コンピュータ)を利用する処理 (いくつかの部門の業務処理のコンピュータ化) |
|
受注センターの設置を指摘 北澤氏は、各部署が行うべき改善案も具体的に提示しているが、特に大きな指摘事項が受注センターの設置である。これは、現在営業部で行われている受注業務を、壜詰製品部に移す事によって、受注担当者の在庫把握が迅速になり大幅な生産性の向上が期待されるというもの。センターの設置には、クレーム処理対策や営業担当との情報交換など解決しなければならない事項も多いが、大きな効果を生むと指摘している。 同社では、今回の指導を受けてこれまでプロジェクト検討会を6回開催、第一ステップ到達を9月に設定している。全社一丸となっての取り組みだけに、情報化以外においても大きな効果を同社にもたらすものと思われる。
後継者自らがシステム開発
 三和コンクリート工業(株)
原価管理に力を入れる
全社的な経営課題
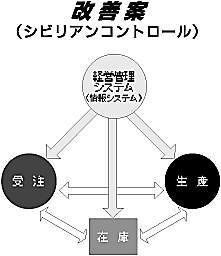
経営課題に対する改善案
情報化に関する問題点
情報化に関する改善案
現在、孝行氏はこれまで原価管理によって求めてきた製品別の製造原価等のデータを取り込んだSANWA.TSS(三和・トータル・サポート・システム)(見積積算・受注管理・販売管理等)を大方完成させたことから、7月からテスト稼動させる計画である。また、今年中には生産管理と在庫管理を盛り込み、一段落つけたいとしている。 一方、在庫の削減について孝行氏は、「現在営業が中心になって在庫削減運動を展開しています。システム的には、受注情報と在庫情報をうまく連携させて、精度の高い生産管理・在庫管理システムを作り、在庫を何とか減らしていきたいと思います」としている。 日常業務と平行した開発であるため歩みはゆっくりだが、三和コンクリート工業の情報化は一歩一歩着実に進んでいる。高性能なパソコンの普及やより開発し易いソフトの出現によって、同社のように社内で自社用システムを開発するケースは今後益々増えてくるものと思われる。同社の事例はそうした企業に非常に参考になるであろう。 |