
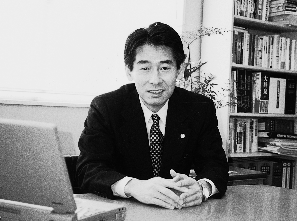 |
経営資源と組織的経営
|
| 税理士 長谷部 光哉 氏 |
|
仕事柄、経営者の方々とお会いする機会が多いというより、むしろ経営者の方々とお会いし、経営上の諸問題の解決のお手伝いをすることが仕事という職業について20年近くになります。昨今の企業を取り巻く成熟化、ボーダーレス化、高度情報化の社会潮流のなかで改めて痛感するのは「自社のもつ経営資源を認識した組織的経営の大切さ」であります。 「秋田の経営者はつくる事や売る事には最大限の経営資源を注ぐが組織的な管理体制の構築は二の次。」といわれています。もちろんこうした批判をうけるいわれのない経営者の方も数多くいらっしゃると思いますが、一面うなずけることも事実です。 つくる事や売る事は経営資源の脆弱な中小企業にとって極めて重要な経営課題ではありますが、ゴーイング・コンサーンを前提とした企業にとっては経営課題の一部に過ぎません。それぞれの業態においてある程度の規模に達した企業は当然として、新規に事業を起こす場合も「まずつくる事、まず売る事」のかけ声の裏側では常に緻密な管理体制の構築もしたたかに成し遂げる能力も求められています。今はもう昔のような誰でも成功の夢にひたれる高度成長期ではないのです。 モノをつくるときは工程管理だけでなく、同時に最終の市場価格を意識した原価管理も必要であるし、モノを売るときは単に一定の掛け率に基づく販売価格で購入してくれる顧客をチャネルととらえている売り方だけでは先が見えてしまいます。もし年商1億円の企業の原価改善を1%、販売価格の改善を1%達成できたら年間約200万円の営業利益を生み法人税引き後で約100万円の余裕資金を借入金の返済等にあてられます。 これは管理による利益のほんの一例です。経営者との会話のなかで「来年度の予定原価率は何%ですか?」「う・・ん。50%前後かなあ・・。」といったやりとりがよくあります。「今年度からはじめた原価管理の成果が来年度にはあらわれ1%改善し48.5%にもっていける自信があります。」こうした答えを聞きたいものです。 また、PL訴訟、取引先の倒産、労災事故、幹部社員の退職等々企業にマイナスの影響を与える様々な要因を未然に防ぐ管理体制も不可欠です。 顧客に交付する製品取扱い説明書や標準売買契約書の整備、債権管理の法的手続、各部署の業務基準の策定、社内の倫理基準の制定等々、企業として極めて当然のことを確実に実行することが必要です。 こうした管理体制の構築は安易に外部の専門家に頼るだけでなく、多少時間と労力を費やしても先ず社内の意見を尊重しながら一つ一つ積み上げていく方がのちのち円滑に機能するようです。 それが現状の一部の有能な社員の個人プレーに頼る経営体制から全員参加の組織的経営体制への転換の好機となるからです。 さて、最後に一言。巷では「アウト・ソーシング」なる言葉が流行のようですが、経営者の方々には、もう一度自社自身のもつ経営資源をみつめ直して戴きたいとおもいます。ヒト(社外のブレーンも含め)、モノ、カネ、そして継続企業にとって有益な情報、過小評価や過大評価がないかどうか、一つ一つ棚卸しをするように……。 |
