
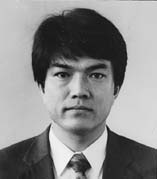 |
経営者の責任
|
| 弁護士 三浦 清 氏 |
|
「はじめて勤めた小さな電気屋さんの経営者が、15歳の自分のことを『松本さん』と呼んでくれていた。年端もいかない自分をこうして大人として扱ってくれたことがとても嬉しかった。」・・・亡くなった作家の松本清張の自伝的な記述でこのようなくだりがあった。人間に対する敬意ということを考えさせられる一文であり、妙に印象に残っている。 弁護士の仕事をしていると、経営者の悩みをお聞きする機会が多いが、ふと漏れた言葉に経営者の重責をしみじみと実感することがある。極端な話、会社が倒産やむなきという事態でも、従業員の給料だけでもとか、取引先にいくらかでも等、少しでも対外的な責任を果たしたいという経営者と接したときには思わず頭が下がる。こういうときに私が「社長」と呼ぶと躊躇らう方が多い。でも、私は、組織の大小に関わりなく、こういう方こそ「社長」と呼ばれるにふさわしい方だと考えている。まさに、事業主体と経営者が一つになるときであるし、会社の危機や崩壊を自らの顔面で受け止めなければならないときだからである。 このような付き合い方が多いせいか、私は、経営者としてその事業を動かしている方に対しては「社長」としての敬意は欠かせないと考えている。組織の一人として事業を動かしているのとは異なり、世間は、組織の「顔」としての評価をするし、また、従業員の生活は経営者の考えや判断で左右もされるからである。それだけの責任を経営者は抱えているということであるし、逆に、経営者は、それだけの自負をもっていただきたいし、相手がどんなに大きな組織の人間であっても自分がトップであるとの威厳をもって接していただきたいとも考える。 しかし、弁護士として今一歩感じることは、経営者の方々は、果たして日常的に危機管理や法務対策といった意識をもっておられるのかという疑問である。というのは、私自身、真に危機が訪れた局面でないと経営者に接する機会が少ないというのが素朴な実感であるからである。同じ肩書資格をもつ職種でも税理士さんや社会保険労務士さんとは異なり、弁護士と日常的な付き合いをされている方は少ないのではなかろうか。これは、一つには、敷居が高いと誤解されている点で弁護士会の宣伝不足もあろうが、弁護士の必要性が訴訟になったとき等の限られたときしか感じられていないということもあるのではないかと思われる。 もちろん、弁護士は、経営や経済の見通しについては全くの素人であるから、ストレートに経営の話をされても役不足である。しかし、弁護士は、経営については最も臆病な人種である。いつも最悪の場合を考えてしまう傾向がある。それゆえ、弁護士を相談相手として持つメリットは、契約書の内容の吟味といった日常的な法律相談以外にも経営的な落とし穴についてのチェック役を持つというところにもあるのではないかと考える。 確かに、高いお金を出して弁護士と顧問契約を結ぶ(といっても秋田弁護士会の場合、事業者顧問料は毎月3万円ないし5万円というのが相場ではなかろうか)までの必要性を感じられている方は少ないとは思う。しかし、日常的に相談相手となる弁護士を持つことは、企業が順調に活動しているときこそ有益なはずだし、弁護士は、事業者の方々とお話をする機会をいつも待っている。すぐ相談できる「顧問的な」(決して顧問契約までの必要はないと思う)弁護士を身近に持つことは、社長の危機管理への考え方を象徴的に示すものである。先月号で危機管理に関連して司法書士さんの有意義なご投稿があった後で、若干手前味噌な宣伝になるかもしれないが、このような身近な弁護士を持つことは、経営者としての責任の一つといえる時代になりつつあるのではないかとも思うのである。 |
