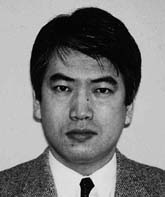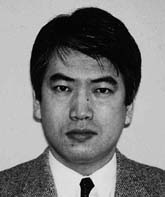最近「ユニバーサルデザイン」という言葉を耳にすることが多くなった。ユニバーサルデザインとは「可能な限り、最大限すべての人に利用可能であるように、製品や建物、空間をデザインすること、またデザインしたもの」であると定義されている。
ユニバーサルデザインの原則として、米国ノースカロライナ州立大学のロナルド・メイス氏は「誰にでも公平に使用できる」、「使う上での自由度が高い」、「簡単で直感的に使用方法がわかる」、「必要な情報がすぐ理解できる」、「うっかりエラーや危険につながらない」、「無理な姿勢や強い力なしで楽に使用できる」、「接近して使えるような寸法・空間である」こと、の7つの項目をあげている。私の専門とする交通計画の分野では、障害者のためのバスがその一例としてあげられる。数年前までは、通常のバスに電動のリフトを取り付けたリフト付きバスが、車いす対応のバスとして一般的であった。車いすの方がこのバスを利用する場合には、乗務員が降りてリフトを操作するため、時間も手間もかかっていた。このような対応は特定のユーザーグループに対するスペシャルデザインであるといえる。これに対して最近では、バスの床面の高さが、道路から30センチ程度の超低床バス(ノンステップバス)が普及している。このようなバスであれば、車いすの方が乗る場合には、簡単な渡し板をかけるだけで自力で乗り込むことができる。また超低床にすることで、今までバスの乗り降りに負担を感じていた高齢者や、ベビーカーを押した人などはもちろんのこと、健常者にとってもバスの利用が容易となる。このようにユニバーサルデザインは、それによって便益を受ける人が増加するばかりでなく、製品や環境の整備コストを低減させることを可能とするものである。
私たちは高齢社会、福祉社会という社会環境を迎えることによって、真に人々に求められる製品や空間、環境を発見する手がかりを得ているのではないだろうか。メイス氏の7つの原則に一つだけ加えるとすれば、それはその製品が機能面においてユニバーサルであるだけでなく、多くの人に受け入れられるような、デザイン自体としての魅力を有していることが重要であると考える。つまり、福祉然とした製品や建物、環境の整備ではなく、「かっこいい」、「使ってみたい」と思うようなユニバーサルなデザインが求められているのではないだろうか。
|