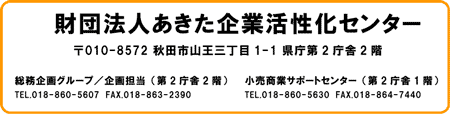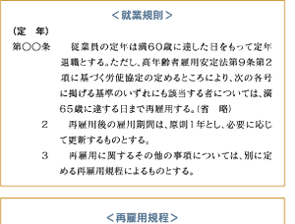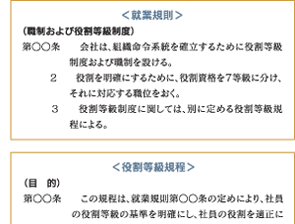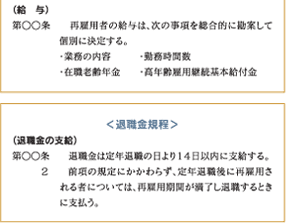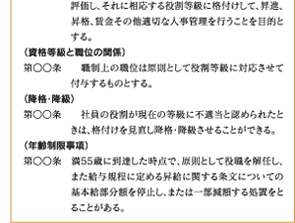|
より良い経営のために迅速、的確な判断・行動力が絶えず要求されている経営者に向けて、県内各分野の専門家が送るメッセージです。
65歳までの雇用延長と賃金設計高年齢者雇用安定法が改正され、事業主は、平成18年度から特別支給老齢厚生年金開始年齢65歳への段階的引上げに対応し、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引上げていくことになりました。65歳雇用延長義務違反に対する罰則等は特に設けられていませんが、雇用延長制度は法律で義務づけられている制度であることから、違反している企業に対してはハローワークから指導・助言を受けることになります。今号では、65歳雇用延長と賃金設計をテーマに社会保険労務士 渡部喜政氏にお話をうかがいました。 |
 |
|
○65歳までの雇用確保措置 65歳未満の定年制を定めている事業主は、高年齢者雇用確保措置として次のいずれかの措置を講じる必要があります(改正法第9条)。 (1) 定年年齢の引上げ(65歳までの引上げ) (2) 継続雇用制度の導入(65歳までの再雇用制度または勤務延長制度) (3) 定年の定めの廃止 65歳までの年齢は、厚生年金支給開始年齢の引上げに合わせ、雇用年齢を平成25年4月1日まで、次のとおり段階的に引上げられます。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
○労使協定等による継続雇用制度対象 高年齢者基準 継続雇用制度について、原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められていますが、各企業では制度の対象となる従業員を限定されているケースが多くなっています。 継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準の定めは、次のとおりです。 (1) 従業員の過半数代表と労使協定により基準を定め、その基準に基づく制度を導入する。 (2) 事業主が、(1) の労使協定のために努力したにもかかわらず労使間の合意が得られない場合は、就業規則等により基準を定め、常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、労働基準監督署長に届け出なければなりません。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
65歳定年延長の最大の課題は、給与体系の見直し(厚労省雇用管理調査)であり、企業が雇用延長を実施する場合、最大の障害は賃金・退職金問題です。 雇用延長を実現するためには、高齢者の生産力と賃金のバランスをいかに調整するのかが避けて通れない課題です。具体的な賃金設計は、60歳以降の適切な賃金調整、60歳以前からの賃金カーブの下方修正、管理職給与の見直しや昇給抑制等がありますが、就業規則の改正については、合理的な変更内容に注意し、特に不利益変更には合理性が求められるため、個々の従業員からの同意等に留意する必要があります。 |
||||||||||||||||
| A社(再雇用制度)の場合 同社は、60歳定年で一度退職させ、以後、フルタイマーまたはパートタイマーとして1年ごとの雇用契約(賃金等はその都度個々に決定する)を締結する。 |
B社(等級・資格制度の改善)の場合 同社は、従来の職能資格制度を廃止し、新たな役割等級制度を導入した。これまでの硬直した人事システムからの脱却により、柔軟な賃金体系による雇用延長が図られ、総人件費の抑制が実現した。 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 高齢者賃金設計に当たっては、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付を併給することから、60歳到達時賃金の61%が最大給付額となることに注目。また、退職金の支払いについては、再雇用満了日に支払うのかを明記する。 | 雇用延長制度導入を機に、これまでの職能資格制度を改め、年功型高資格等級、高賃金の構造を改善し、役割等級制度を新設して総人件費のコスト減を図った。 なお、50歳代既得権者を保持し不利益変更を回避した。 |