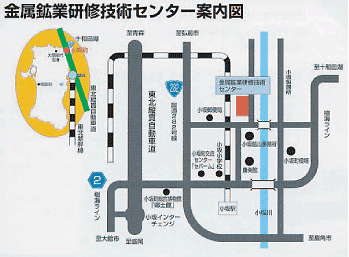|
 |
|||
秋田県では、「あきた21総合計画」第3期実施計画(平成18年度から20年度)において、秋田の強みを活かした産業の振興の一つとして、鉱山技術に裏打ちされた『資源リサイクル産業の拡充』への取り組みを行っております。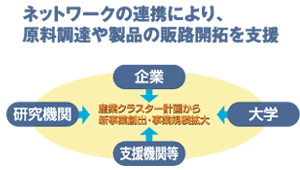 また、経済産業省は各地域で競争力基盤の形成を図る産業クラスター*1 計画を平成13年度から実施しており、東北管内では「循環型社会対応産業振興プロジェクト」などを推進してきております。平成18年度からは、これまでの全国19プロジェクトを見直し、第II期「クラスター計画」(平成18〜平成22年度)として、17プロジェクトに再編し推進することになりました。東北では「TOHOKUものづくりコリドー」*2 として実施されることになり、重点産業分野として「非鉄金属リサイクル分野」も重点7分野の1つとして取り上げられております。また、推進組織の株式会社インテリジェント・コスモス研究機構に連携する拠点組織として、秋田県では財団法人あきた企業活性化センターとともに、「財団法人秋田県資源技術開発機構」が位置づけられております。
また、経済産業省は各地域で競争力基盤の形成を図る産業クラスター*1 計画を平成13年度から実施しており、東北管内では「循環型社会対応産業振興プロジェクト」などを推進してきております。平成18年度からは、これまでの全国19プロジェクトを見直し、第II期「クラスター計画」(平成18〜平成22年度)として、17プロジェクトに再編し推進することになりました。東北では「TOHOKUものづくりコリドー」*2 として実施されることになり、重点産業分野として「非鉄金属リサイクル分野」も重点7分野の1つとして取り上げられております。また、推進組織の株式会社インテリジェント・コスモス研究機構に連携する拠点組織として、秋田県では財団法人あきた企業活性化センターとともに、「財団法人秋田県資源技術開発機構」が位置づけられております。財団法人秋田県資源技術開発機構*3 では、経済産業省の広域的新事業支援ネットワーク拠点重点化事業、東北経済産業局のクラスター計画「循環型社会対応産業振興プロジェクト」として、地域の経営資源を活用した新たな技術の開発と新事業の創出を目指し、平成16年度より『資源リサイクル産業クラスター形成事業』を実施しております。 |
|||
|
|||
|
1. 事業目的
 秋田県では、かつて沿岸地帯で石油・天然ガス鉱山、内陸部では非鉄金属鉱山と林業が地域経済を牽引してきました。しかし、昭和60年のプラザ合意以降、国際相場の非鉄金属価値が暴落。採鉱量が減少し、平成6年にはすべての鉱山が閉山を余儀なくされました。木材産業も同様に衰退し、バブル崩壊も追い打ちとなって誘致企業が撤退するなど、地域は雇用の場を失い、人口減少に歯止めがかからない状況に陥りました。
秋田県では、かつて沿岸地帯で石油・天然ガス鉱山、内陸部では非鉄金属鉱山と林業が地域経済を牽引してきました。しかし、昭和60年のプラザ合意以降、国際相場の非鉄金属価値が暴落。採鉱量が減少し、平成6年にはすべての鉱山が閉山を余儀なくされました。木材産業も同様に衰退し、バブル崩壊も追い打ちとなって誘致企業が撤退するなど、地域は雇用の場を失い、人口減少に歯止めがかからない状況に陥りました。こうした状況下で、秋田県では、平成7年度から国(旧通商産業省)の指導を受けながら、リサイクル・マイン・パーク事業をすすめ、平成10年度には秋田県北部エコタウン計画を策定し、平成11年11月に国(旧通商産業大臣、旧厚生大臣)の承認を得ております。(平成16年10月には国(経済産業省、環境省)から変更承認を受けております。) 秋田県北部エコタウンエリアでは、これまで鉱業、林業等で培われた製錬技術、リサイクル技術、廃棄物処理技術、木材加工技術、優れた人材、施設などを活用した資源リサイクル関連事業の創出が図られ、一定の成果が現れています。 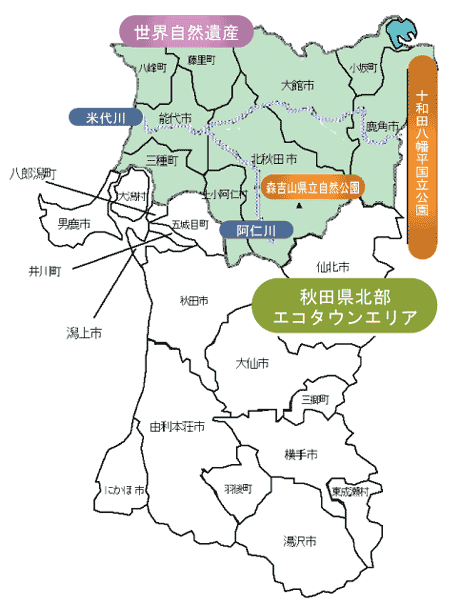 今後こうした優位性のある経営資源をさらに活用し、新たな技術開発や新規事業化による地域経済の活性化や雇用の拡大を図るとともに、豊かな自然と共生する環境調和型社会を形成していくことが課題となります。 今後こうした優位性のある経営資源をさらに活用し、新たな技術開発や新規事業化による地域経済の活性化や雇用の拡大を図るとともに、豊かな自然と共生する環境調和型社会を形成していくことが課題となります。こうした課題に対応するための具体的な取り組みとして、当機構では「資源リサイクル産業クラスター形成事業」を実施し、秋田県北部エコタウンエリアを中心に、金属や鉱物など資源リサイクル関連の新技術の開発や、環境を柱とした新たな産業の創出をめざしています。資源リサイクルに意欲のある企業、研究機関、大学、支援組織等によるネットワークを形成し、それに対する原料調達や製品の販路開拓の支援を行っています。同時に、廃棄物等からリサイクル製品をつくり出す調査や技術開発を支援し、新産業創出による経済雇用効果の発生を図っております。 |
|||
|
2.事業内容
●資源リサイクルネットワークの形成
県北部を中心としながら、全県域を対象として資源リサイクルを積極的に事業化している、又はしようとする企業、研究機関、大学、市町村等に呼びかけて会員を募集しております。(会員数120社を目標に会員を募集中です)会員企業等の原料調達から製品販売までのマッチングを支援しております。また、開発したリサイクル製品の販路を求める企業等の商品PRを図るほか、推進組織と連携し、専門商社等を紹介して販売開拓を促進しております。 ●金属リサイクル等の推進
 金属リサイクルについては、製錬企業等を核とした事業展開が期待されております。最終的に金属を高純度地金にリサイクルすることが可能なのは製錬所であることから、様々な金属含有物を分離、分別、前処理によって濃縮し製錬所に集める過程で、新たな事業の創出が期待されます。
金属リサイクルについては、製錬企業等を核とした事業展開が期待されております。最終的に金属を高純度地金にリサイクルすることが可能なのは製錬所であることから、様々な金属含有物を分離、分別、前処理によって濃縮し製錬所に集める過程で、新たな事業の創出が期待されます。自動車関連、電気電子部品関連など金属を含有する廃棄物やロットアウト品、メッキスラッジなどの資源量調査を行い、研究会を設置するなど、再資源化の可能性を追求しています。 このほか、地域で課題となっているスラグの再資源化、水素社会に向けた燃料電池のリサイクルについても調査、検討しております。 ●研究会等の開催
関連する研究会の立ち上げ、セミナー、交流会などを行い、産学官の連携を強化するとともに、資源リサイクルに関する情報の受発信を行っています。
●販路支援開拓事業
リサイクル素材を用いた製品の販路開拓のため、会員企業等における情報の受発信を活性化させ、効率よくマッチングが行われるよう支援しております。
●情報提供事業
産業クラスターについての最新情報を提供し、会員の増加を図っております。 |
|||
|
3.これまでの事業実績
●ネットワーク形成事業
現在の会員数は次のとおりです。◎拠点企業会員数 63社(うち個人2名) ◎支援組織機関数 9団体 ◎連携大学研究機関 8機関 ●新商品・技術評価事業
県内の製錬所やレアメタル回収施設における事業の実態、鉱種ごとの需給動向を把握し、今後の循環型非鉄金属産業の構築に向けた方向性(新たな鉱種、原料の開拓等)を検討するため、金属リサイクル可能性賦存量調査を委託実施しました。また、地域内の廃棄物需給動向を調査するため、会員企業等を対象にアンケート調査を実施したほか、今後の事業展開のための調査を行っております。 ●連携促進事業
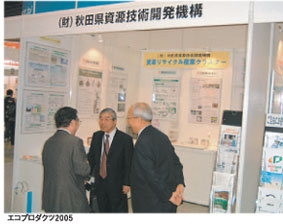 溶融スラグの再資源化について、問題点の整理と課題解決を図るため研究会を設置し、情報と意見の交換を行っております。
溶融スラグの再資源化について、問題点の整理と課題解決を図るため研究会を設置し、情報と意見の交換を行っております。また、地域企業の連携と交流促進を図るため、秋田県北部テクノプラザや東北経済産業局と連携し、セミナー等を開催しております。 ●販路開拓支援事業
会員の展示会(エコプロダクツ2005)などへの参加を支援しております。
●情報提供事業
ネットワーク形成を推進するため、パンフレットや、地域におけるリサイクル関連技術と企業の集積とネットワークを示したリサイクルマップを作成しております。
|
|||
|
4.事業効果
会員には、拠点組織の会員となることで推進組織のビジネスマッチング、相談会、展示会、広域的な人的ネットワークに参加する機会が増加するというメリットがあります。会員相互間や、会員と支援機関間で、原料調達や販売促進などについての有益な情報交換が行われること、また、企業訪問などの交流により、技術の開発や新事業創出の機会が増加することが期待されます。地域では、新たな技術が開発され新産業が創出されることにより、雇用増加や人口減少への歯止めにつながると考えられます。同時に、廃棄物等の減量化と環境負荷の軽減が図られ、循環型社会の形成に寄与することができるものと期待されます。 |
|||
|
5.ビジネスチャンスは「秋田」から
資源リサイクル産業クラスター事業は、企業同士や関係する機関・大学等との交流を通じて、良い意味での企業間・地域間競争を基盤とした地域全体の経済成長を目指しています。産業クラスターを形成する上で、地域内の企業が対等の立場で協力・競争し合う成熟した関係を構築することなど、「競争」と「連携」が重要なポイントとなるのはもちろんですが、それに加えて地域の潜在能力を有効活用することも大変肝要です。 秋田では、古くから鉱山技術、それに関連する高度製錬技術の開発・蓄積が図られてきました。特に非鉄金属分野では17種類ものメタルを回収、供給できるトップクラスの技術があります。その高度技術は、廃家電や使用済廃自動車などからの有用金属の分離回収、廃棄物処理施設から排出される処理灰からの希少金属の再資源化、廃棄物の極小化等、環境に関する課題の解決に有効であると期待されています。その他にも、汚染土壌処理技術、廃液処理技術、廃木材・廃プラスチックの再資源化技術、焼却灰・スラグ有効活用技術等、環境産業に対応した様々なポテンシャルが蓄積されています。『資源リサイクル産業クラスター形成事業』では、これらの技術を活用し、ものづくりである「動脈系産業」と廃棄物をリサイクルする「静脈系産業」を結びつけることで、循環型社会の形成を目指しています。  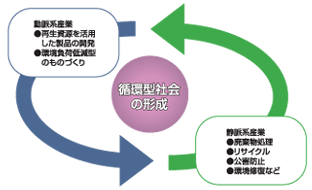 |
|||
|
6.入会の御案内
 入会しているだけでも、補助金・研究開発制度の公募情報やマッチングアライアンスに関する情報など、有用な情報を受け取ることができます。
入会しているだけでも、補助金・研究開発制度の公募情報やマッチングアライアンスに関する情報など、有用な情報を受け取ることができます。入会ご希望の方は「入会申込書」に必要事項をご記入のうえ、当機構までお申し込みください。入会申込書はホームページに掲載しています。 |
|||
|
財団法人 秋田県資源技術開発機構
〒017-0202 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館9番地3 (金属鉱業研修技術センター内) TEL 0186-29-3100 FAX 0186-29-3840 e-mail:kikou@ink.or.jp |
|||
|
[参考]金属鉱業研修技術センターのご紹介
 金属鉱業研修技術センターは、秋田県産業技術総合研究センター 工業技術センター、財団法人秋田県資源技術開発機構、財団法人国際資源大学校、及び独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 金属資源技術研究所の4機関のほか、指定管理者を加えた5つの組織を総称したものです。
金属鉱業研修技術センターは、秋田県産業技術総合研究センター 工業技術センター、財団法人秋田県資源技術開発機構、財団法人国際資源大学校、及び独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 金属資源技術研究所の4機関のほか、指定管理者を加えた5つの組織を総称したものです。5機関それぞれが、各機能を連携しかつ補完しながら、全体としては研究開発、研修、学術・国際交流などの各事業を有機的に実施しています。 財団法人秋田県資源技術開発機構は、秋田県北部エコタウン計画の推進を図るとともに、資源リサイクル等に関する研究支援、普及啓発、研修、人材育成、各種交流事業などを行い、県内における資源リサイクル関連産業の振興発展及び地域の活性化を図るため、次の事業を実施しております。 ※平成2年11月設立、平成3年1月業務開始
1 研究支援事業
 ●有用金属の効率的回収技術の研究(企業との共同研究)
●有用金属の効率的回収技術の研究(企業との共同研究)資源リサイクルを活発化し、事業化に結びつく研究を支援 しております。 2 資源リサイクル普及啓発事業
●エコタウンセンター機能の充実環境・リサイクルについての展示コーナー、見学コースを設 定して普及啓発を行い、資源産業と環境の調和による循 環型社会形成を推進します。 3 交流事業
●大学や試験研究機関との連携や情報交換等による、学術 交流や科学実験室などを開催
4 研修事業
●地域企業等を対象に分析機器の操作方法等に関する研 修を実施(秋田県工業技術センターの協力により実施)●資源関連企業等の技術相談・指導等の仲介 ●財団法人国際資源大学校への研修支援 5 広域的新事業支援連携等事業
●資源リサイクルを中心とした産業クラスター形成の推進(資 源リサイクル産業クラスター事業:経済産業省補助事業)
≪その他の機関について≫
 ●秋田県産業技術総合研究センター
●秋田県産業技術総合研究センター工業技術センター リサイクル技術開発グループ ※ 平成17年度より(財)秋田県資源技術開発機構の研究部門を編入 ◎リサイクル技術の開発 研究機器・研修室・会議室もご利用いただくことが出来ます ●財団法人国際資源大学校(MINETEC) ※平成3年1月、静岡県富士宮から小坂町へ移転 ◎海外技術者研修(JICAほか) ●独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 金属資源技術研究所(JOGMEC MTC) ※平成7年10月設立 ◎バイオリーチング技術の開発 ◎環境に係る調査研究ほか  ●指定管理者(株式会社アルバートホテル小坂)
●指定管理者(株式会社アルバートホテル小坂)※平成18年4月から指定管理者制度により宿泊棟、レストランを管理・運営 ◎宿泊棟「小坂ゴールドパレス」の管理・運営 シングル38室、ツイン2室、ゲストハウス : ツイン6室 ◎レストラン「青銅館」の管理・運営 年間を通じて一般の方にもご利用いただくことが出来ます |
|||
|
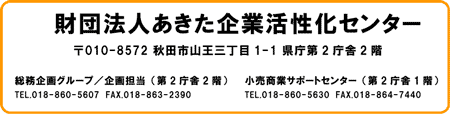
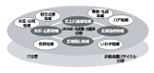 東北地域がダイナミックに発展するためには7技術・産業分野と10産業集積地域が有機的に連携し、それぞれの強みを持ち寄り相乗効果によってクラスター形成の早期実現を目指すことが重要とされています。その点を重視し、平成18年度から展開するプロジェクトが「TOHOKUものづくりコリドー」です。
東北地域がダイナミックに発展するためには7技術・産業分野と10産業集積地域が有機的に連携し、それぞれの強みを持ち寄り相乗効果によってクラスター形成の早期実現を目指すことが重要とされています。その点を重視し、平成18年度から展開するプロジェクトが「TOHOKUものづくりコリドー」です。