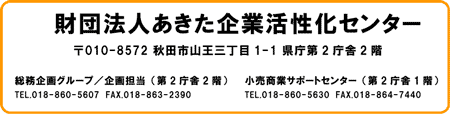|
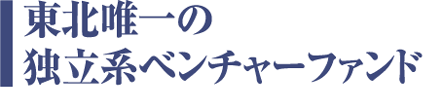 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2002年2月から始まった現在の景気拡大期が、戦後最長だった「いざなぎ景気」(65年11月〜70年7月=57カ月間)を超えることがほぼ確実視されている国内経済であるが、ものづくり産業を支える中小製造業界は、原油価格の急騰等による減益が進み、低迷を余儀なくされています。このような状況が特に東北地域で顕著であることが、依然として国内経済の地域間格差が大きいことを物語っています。こうした局面を打開するためには、雇用を生み出し、有効需要を創出し、地域経済の活性化に直結する地域ベンチャー企業の誕生・育成が急務であると考えられます。 今回の特集では、従前からこうした考えに立ち、東北の未来と技術を応援する東北唯一の独立系ベンチャーキャピタルである東北イノベーションキャピタル株式会社の東北地域経済活性化への取組についてご紹介します。 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
東北イノベーションキャピタル株式会社は、元日興キャピタル代表取締役社長の熊谷功氏が中心となって、平成15年10月に設立した東北地域密着型の独立系ベンチャーキャピタルである。実は、それまで東北地域を拠点とする独立系ベンチャーキャピタルは皆無であり、設立の当時から、当社のビジネスモデルは東北地域内で大いに話題を呼んだ。
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
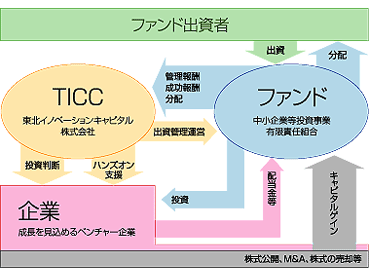 1. 東北イノベーションキャピタル株式会社のビジネスモデル
1. 東北イノベーションキャピタル株式会社のビジネスモデル |
|||||||||||||||||||||
|
2.投資先企業への支援
上記ビジネスモデルにおける東北イノベーションキャピタル株式会社の役割は、いわゆるファンド運営団体としての「投資事業有限責任組合」の管理運営である。中心となるのは、「成長が見込める」企業の発掘、投資判断、そして投資先企業への地域密着型ベンチャーファンドならではの支援を行う業務であり、これらの概要は次のとおりである。
(1)ファインディング
東北地域密着型のベンチャーキャピタルならではのネットワークやフットワークを活かし、企業のシーズ段階から発掘し、直接訪問、経営者への面談等を行いながら、投資先候補を選定する。
(2)デュー・デリジェンス(投資審査)
ビジネスモデル、ビジネスプランの検討、技術・製品・サービスの市場性評価、財務状況の精査等、専門的なデュー・デリジェンスを実施する。
(3)投資の実行
分散型投資により、シーズ段階、初期段階の企業への投資にかかるリスクを回避する。個別の企業への投資は「マイルストーン型投資(事業の発展ステージ応じた段階的な投資)」を基本に、投資先企業の発展段階に適合した投資を実行する。
(4)ハンズオン(経営支援)
CEO(Chief Executive Officer:最高経営責任者)、CFO(Chief Financial Officer:財務担当責任者)の斡旋、ビジネスパートナーの紹介を始めとした投資先企業の成長ステージに見合った経営支援を積極的に行う。さらにIR活動に関するアドバイス、株式公開に向けてのノウハウなど、多面的な支援を行う。
(5)EXIT(出口:投資の回収)
投資先企業の株式を株式公開後に売却すること等により、キャピタルゲイン(株式価格上昇から生じる利得の還元)を実現する。また、M&A等の手法を通じ、より有利な出口を判断し投資利益を獲得する。
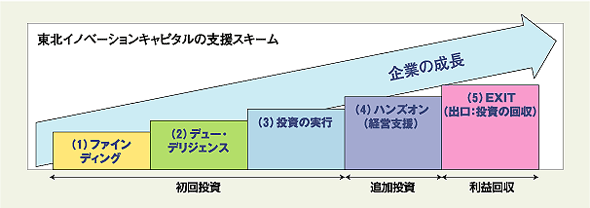 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
前述の取り組みを具体化した東北イノベーションキャピタル株式会社の第1号ファンドが、平成16年3月設立の「東北インキュベーション投資事業有限責任組合(東北インキュベーションファンド)」である。
大学発ベンチャー企業を中心とするエレクトロニクス、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー等のハイテク分野に投資先を絞り、東北6県に新潟県を加えた7県に事業拠点を有する企業を対象として投資先企業を選定した。平成18年8月現在、既に22社に対して約23億円の投資を実行済みで、このうち1社がM&Aにより株式売却済み、もう1社がジャスダックに上場しており、東北インキュベーション投資事業有限責任組合(東北インキュベーションファンド)が所有するこの企業の株式の半分を売却し、出資者に利益分配を実施している。他の20社に対しては、今後の株式公開に向けていわゆるハンズオン支援を強化していくこととなる。
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
東北イノベーションキャピタル株式会社が発足して3年目を迎え、第1号ファンドによる投資活動を通じて、関係者は少なからず自らの東北経済活性化への取り組みに手応えを感じている。その理由として、リスクマネーの供給がベンチャー企業の成長にとって重要な役割を担っているのだとの再認識されたこと、特に、東北地域に多く見られる経営資源の乏しいベンチャー企業には、投資することのみならず、その後のケア、つまりハンズオン型の経営支援が重要であり、そのような取り組みが高い効果を発揮したことが挙げられる。そして、このことはベンチャー企業だけでなく、東北地域における製造業系の中小企業にもあてはまるとの判断により、平成18年(2006年)8月31日、第2号ファンドとして「東北グロース投資事業有限責任組合(東北グロースファンド)」を立ち上げるに至った。
東北グロースファンドは、独自の技術やビジネスモデルを持ち、今後の急成長が期待でき、株式公開の可能性があり、東北地域の経済活性化に寄与できるような企業が投資先となる点に違いはないが、東北インキュベーションファンド(第1号ファンド)が大学発ベンチャー企業を中心とするハイテク分野に投資先を絞っていたのに対して、東北グロースファンドの投資先は、50%がベンチャー企業、残り5 0%がベンチャー企業以外の株式未公開企業に対する投資を計画していることが特徴的である。
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
東北イノベーションキャピタル株式会社の意気込みや東北地域に対する思い入れ等を、代表取締役 熊谷巧氏に伺った。
○どのようないきさつで東北イノベーションキャピタル株式会社を立ち上げたのでしょうか。
東北地方には、大学等を中心としてさまざまな有望シーズが埋もれています。時代とともに、行政機関を中心とした支援機関、支援制度も充実してきて、ベンチャー企業の創出、成長、発展が期待できる環境が東北地方に整ったと言えた時期でした。その頃に、地元の方々からお声掛けいただくことになりまして、「あとは何を整えれば、潜在しているシーズやベンチャー企業を成長発展させられるか」自分なりに考えたところ、それはリスクマネーの供給であると感じたわけです。
こうしたことから、国内外での投資経験豊富な人材と、技術などの目利き人材が参画する東北地域密着型のベンチャーキャピタルを立ち上げ、第1号ファンドは「東北地域」と「大学発ベンチャー」にターゲットを絞りました。 ○第2号ファンドは、従来のファンドを継続する部分と、新たに既存未公開中小企業への投資も計画されているようですが、ここではどういった思惑があるのでしょうか。
東北地域の経済活性化に寄与するという基本理念に変わりありませんが、地域の支援機関や金融機関等との連携を深めながら、企業発掘、投資、支援がより展開しやすい形態を模索しました。1号ファンドを運用する中で、ハイテクベンチャー企業以外にも、長年の努力によって高い技術力と実績を有する既存企業が多数あることを手応えとして強く感じていたのです。こうした、地域で頑張っておられる企業にも投資ができるファンドにしようということです。
○投資判断として「独自の技術やビジネスモデルを持ち、急成長が期待でき、東北地域の経済活性化に寄与できるような企業」との視点があるようですが、既存企業が投資先として選定される場合、具体的にどのような企業があてはまるのでしょうか。
例えば、これまで大手企業の下請け的な仕事をしながらも、自社の技術を磨き上げ・蓄積している地域の有力企業、一定の事業基盤や独自の技術を有しつつ、新たに大学のシーズを取り入れる、あるいは他企業との連携により一層の成長を模索している企業、株式公開の実力がありながら、これまでそれにトライすることを躊躇していた企業等、様々なケースが想定されます。
今後の国際競争に打ち勝っていくためには、株式公開を通過点として更なる飛躍を目指す、といった強い意欲を持つ経営者であることも重要なポイントです。 ○秋田県内のベンチャー企業、中小企業に一言お願いします。
東北では、秋田県をはじめ、地元金融機関も独自でファンドを組成されているほか、様々なビジネス・マッチングが開催される等、新規事業や地元企業を支援する取組が活発であると思っています。また今年6月には(株)インスペックが東証マザーズに上場したことを契機に、後に続く企業が誕生して欲しいとの期待が高まっていることも感じます。当社としても、県内の関係機関の皆様の協力をいただきながら、第2号ファンドを活用してベンチャー企業や中小企業さんの飛躍のためにお役に立ちたいと考えております。
投資を実行、あとは各企業の努力、というパターンではなく、ハンズオン支援により、より深く投資先企業と関わっていく東北イノベーションキャピタル株式会社の手法は、まさに東北地域のベンチャー企業、中小企業にとって、まさに革新(イノベーション)的なものである。この手法は、新たな企業支援策を模索する行政側にとっても良い参考例となるであろうし、県内企業、特に従来型の製造業界にとって補助金、融資のほかに事業資金獲得策の選択肢が増えることは朗報である。 |
|||||||||||||||||||||