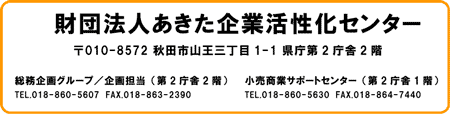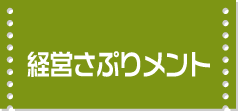
|
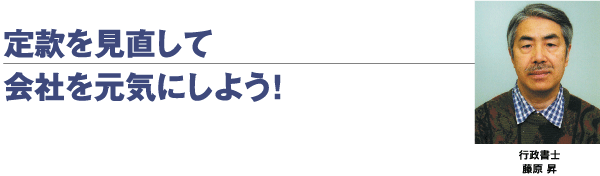 |
|
|
特に株式会社については、選択の自由を増やし定款自治の拡大をすすめています。定款を見直す(変更する)ことで、実態に合った会社のあり方が実現できるようになりました。そこで、定款の見直しから様々な問題を発見し、その解決を考えることが会社を元気にするきっかけになります。 会社を元気にする仕掛けの宝庫、会社法の一部をご紹介します。 また、旧商法で設立された既存の株式会社は、株主総会、3人以上の取締役、取締役会、監査役が必要な機関でした。しかし、会社法では、株主総会と取締役1人だけが必要で、取締役会や監査役の設置は任意です。しかも、取締役1人でも代表取締役の登記ができます。会社の規模、対外的な信用等から取締役会や監査役が不要であれば、登記の費用はかかりますが、定款を変更してそれらを廃止することができます。 今度の定時株主総会で、役員の任期も含め定款の見直しを進めるのが良いと思います。決算の承認とともに、会社法に適合させる定款の整備を準備しておくには、ちょうど良い時期です。なお、どの既存会社も会社法で決算書類の様式が変更になります。 新たな事業形態としてLLP(有限責任事業組合)やLLC(合同会社)の利点が、盛んに言われています。しかし、既存会社でも他の共同事業者に議決権のない株式を譲渡する等、議決権や配当を工夫すると、経営権はそのままに既存事業の強化、共同のブランドによる商品販売、異業種の組み合わせによる新規事業等が可能になります。 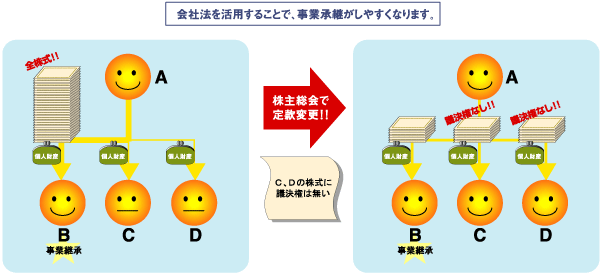 また、会社の種類にかかわらず全ての会社で社債が発行できます。私募債の発行が容易になり、資金調達の有効な方法の一つとなります。 たとえば、1人株主Aに対して推定相続人B、C、Dがいます。Bが事業承継に最適なので、AはBに会社経営のために全株式を相続させたいと考えています。しかし、A個人の株式以外の財産がC、Dの法定相続分に著しく足りず、C、Dに不公平な相続になる場合があります。その場合、Aの株式をC、Dの相続分に相当する分、議決権のない株式として相続させることができます。C、Dには、議決権はありませんが配当を受ける権利はあり、妥当な遺産の分割方法の指定が可能となります(相続税は考慮していません)。手続きとしては、株主総会で定款を変更し、会社が株主名簿にC、Dには議決権がない旨を記載します。Aは、議決権のある株式をBに、議決権のない株式をC、Dに相続させる遺言をします。相続後の対策として、相続で会社にとって好ましくない者が株主になるのを防ぐため、定款に、会社が相続人に対して株式の売渡請求権があると規定することが可能です。 会社法は、非公開会社の場合には、譲渡以外の相続等で株式を取得する者が現れ、株式が分散して会社経営が不安定になる心配をなくすような配慮をしています。 行政書士は、株主総会議事録作成、定款作成や変更、遺言書の文案作成の助言等、できることはささやかですが、会社や人生のたいていのことに深いかかわりがあります。 皆様の身近で便利なかかりつけの相談相手として、あるいはセカンドオピニオンとして、他の専門家とともに行政書士を利用していただければ幸いです。 |