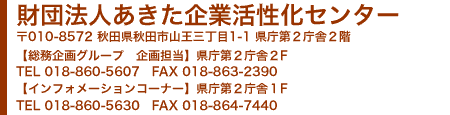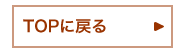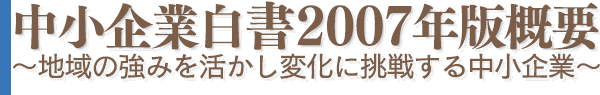 |
| 中小企業庁から2007年版の『中小企業白書』が発表になりました。「〜地域の強みを活かし変化に挑戦する中小企業〜」と題し、第1部では2006年度の全体動向、第2部では地域資源の活用状況や金融機関との関係、第3部では取引形態の変化や人的資本確保の現状を解説しています。 今号の特集では、各章や全体の「まとめ」を元にそれに関する図表とともにその内容をいち早くご紹介いたします。 |
2002年第1四半期を景気の谷とした今回の景気回復は、輸出主導で始まり、民間設備投資によって支えられる形で、長期間にわたり続いてきた。輸出に直結した輸送機械、一般機械などの機械関連業種が集積する地域が活況を呈する一方で、従来からの公共事業に依存してきた地域は景況感、雇用指標において改善幅が小さくなっており、地域間のばらつきが見られる。 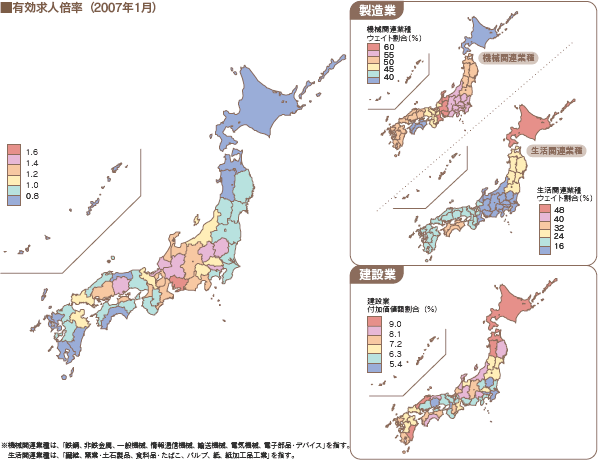 |
開業、廃業の動向については、「タウンページデータベース」を用いることにより、「情報・通信」や、人材派遣などの「事業活動関連サービス」の分野で、これまで把握されていた水準よりも、高い頻度での開業と廃業が起こっていることが分かった。また、開業の担い手も「家業的」な個人商店や町工場のような形だけでなく、大学出の大企業出身者のスピンアウト開業など、多様な人材による開業が起こっていることも確認できた。今後も様々な担い手により、様々なスタイルの開業が生まれるだろう。そうした開業自体が、新たな需要を呼び込み、市場の拡大につながっていくことが期待される。 現在、消費者、企業共にニーズの多様化が進展している。今後経済成長が継続し、サービス経済化が進展すれば、それに伴いニッチ市場も多く生まれることが予想される。こういった市場の変化は、創業、開業の新たなチャンスとなるだろう。また、市場の変化に柔軟に対応できる小規模企業にとっても、活躍の場の広がりが期待されるところである。 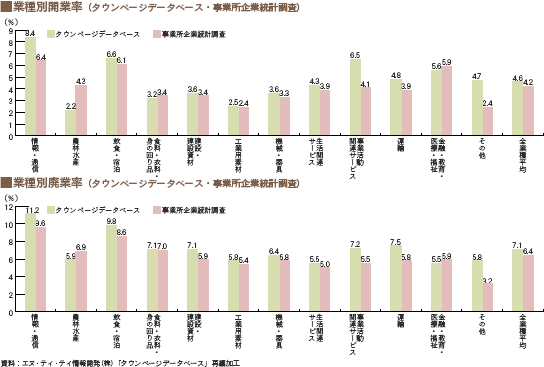 |
地域資源の活用は付加価値や販売数量を増加させるなど、企業経営にプラスの効果を与えるとともに、地域の活性化にも繋がると認識されている。 地域資源を認識している割合は、「観光型」で9割、「農林水産型」で6割、「産地技術型」で3割と、大きな差があったが、いずれの場合も、地域資源が地元の特産・特色であったことが、地域資源活用のきっかけとして高い割合を占めている。地元が持つものの市場価値を、まずは地域の中小企業が十分に認識して、外部の意見も参考にしつつ活用していくことが必要である。 消費者のニーズが多様化している中では、「地域」自体が差別化されたものとなる。改めて地域を見直し、地域資源の活用により地域内外の需要を取り込むことで、中小企業の持続的成長と地域全体の活性化が図られるであろう。 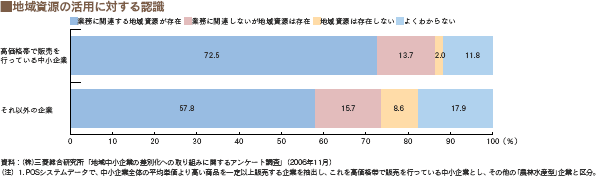 |
クリーニング、理容・美容等のサービスや飲食、生鮮食料品においては、中小小売事業者等が多く消費者に利用されている。今後は、安全・安心をより重視する消費者のニーズの高まりや、一人暮らしの高齢者の見回り、配食などの付加的サービス需要への対応が中小小売事業者等に求められている。清掃、防犯、催事など、地域づくりへの期待も存在する。 中小小売事業者等への期待は、商品・サービスの提供にとどまらない地域づくりの担い手としての役割へと高度化してきている。その実現に向けては、個々の中小小売事業者等の取組に加え、関連事業者、市民、行政との連携、協働が不可欠である。人口減少、高齢社会という新たな時代を迎えている今、暮らしやすい社会、豊かな生活の実現に向けて、各地域に根ざす中小小売事業者等には、新たな事業、新しい仕組みづくりへのチャレンジが求められている。 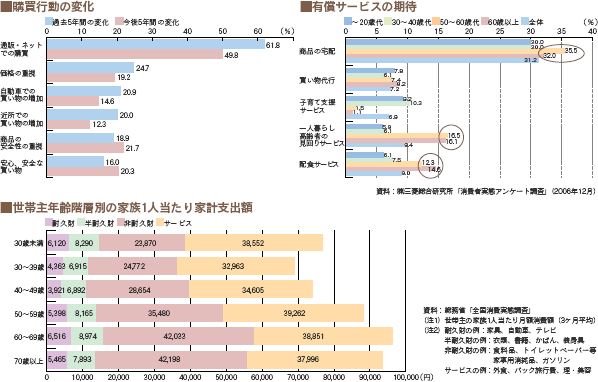 |
10年前、20年前と比較すると、中小企業と金融機関との接触頻度は低下の傾向にある。しかしながら、近年における資金繰り環境の好転もあり、企業のメインバンクとの取引に対する満足度は高まっている。 一方、小規模企業では、特に都市銀行等と取引している場合において、接触頻度の低下が見られる。これは、小規模企業におけるメインバンクとの取引満足度が高まらず、メインバンク変更の頻度が高い要因となっているのではないかと考えられる。複数の金融機関と取引を行う中小企業は、借入額が増加する傾向にあるが、これは、借入依存度の高い企業、債務償還年数の長い企業を中心に、一部の中小企業においては、複数行取引をすることで、資金面の安定性を確保している可能性がある。 中小企業に対する円滑な資金供給を実現するために、従来の不動産担保や保証人に依存した借入以外の様々な手法が導入されている。中小企業においては、これらの利用が更に進むことが期待される。 |
企業の仕入先、販売先は増加傾向にあり、取引構造はますますメッシュ化している。メッシュ化が進展していく中で、同時に企業同士の情報のやりとりは緊密化する傾向にあり、両者を両立させている企業は売上げが堅調に推移している。両者を両立させている企業は、安定した品質を求められる製品の製造や技術交流を行うことによって、他企業と製品の差別化が行えているものと考えられる。単に取引先を増やすだけでは、企業にとって売上高の増加に結び付かない。製品の差別化や技術交流に努め、情報のやりとりをより緊密化し、企業同士の交流を深めていくことが、今後の中小企業にとって重要である。 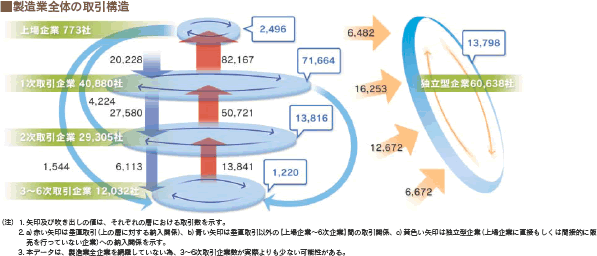 |
我が国において取引構造の「メッシュ化」が進展し販売先が多様化することは、価格決定や取引条件の書面化などに関しては中小企業にプラスの影響を与えている場合が多いが、技術・ノウハウや知的財産の保護といった面では中小企業に対してマイナスに作用する可能性が高いことが明らかになった。さらに、販売先の多様化により、企業間信用取引において、サイトの長さを考慮した価格設定が広まっていく可能性が高まることも示唆された。 我が国の製造業が競争力を高めていくためには、「受注−発注」企業間で共同し、技術や技能を磨いていくことが必要である。 受注側においては、自社製品の原価計算を正確に行うことが大前提となる。加えて、製品の差別化や販売方法の工夫という、製造業が成長するために必須の経営努力を継続していくことも重要である。また、個々の取引について、取引条件を書面で明確にすることで、不利な取引条件を強いられるリスクを回避できると考えられる。 発注側においては、受注企業が提供する製品の適正評価が長期的には自社が属する産業の基盤の維持・強化につながるとの認識のもと、取引条件の交渉を行うことが必要である。 しかしながら、企業間の望ましい取引関係を構築していく上では、業界の取引慣行、企業間の力関係、系列取引内での暗黙のルールなどの様々な障害があり、当事者同士だけでは取引条件の改善を進めていくことが難しいケースも存在する。この場合は、行政や業界団体など第三者の関与が必要となろう。 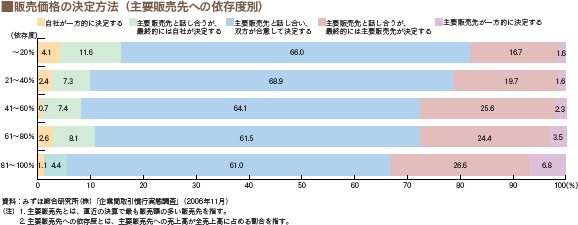 |
近年、我が国の景気が回復しつつある中で、中小企業の採用環境は厳しさを増してきている。今後、中小企業が競争力を持って成長を続けていくためには、個々の企業においてキーパーソンに代表される中核人材を育成していくことが重要である。 また、キーパーソン人材の育成に際しては、その候補者を確保していくという視点から、長期的な雇用が前提とされる正規雇用者の裾野を広げ育成していくことも重要である。一方で、採用環境が厳しさを増していることを踏まえると、高齢者や女性の雇用や、非正規雇用者を正規雇用へ登用するなど採用対象の裾野を広げ、自社での育成に力を入れていくことが望まれる。 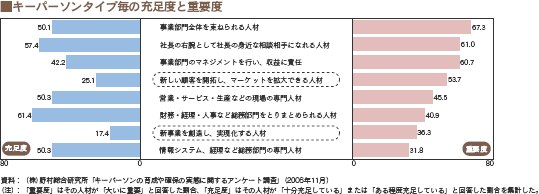 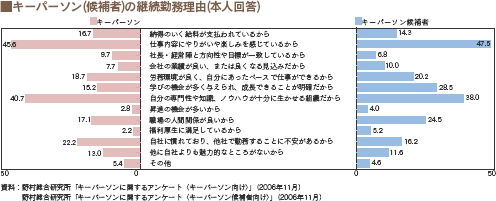 |
今回の分析における議論の出発点は、「我が国企業の業況が全般として回復する中で、地域や中小企業にその利益が行き渡らないのはなぜか」という視点である。大企業と中小企業の間や、地域間で生じている「ばらつき」は何が要因であり、どの程度深刻な問題なのか。今回は、これらについてデータに即して明らかにしようと努めた。 この観点から、例えば、第1部第1章では、主として中小企業が担う消費財関連需要が伸びず、相対的に大企業と関わりが深い設備投資や外需関連の需要が伸びている点、中小企業では価格転嫁が難しい点を示している。その上で、第3部第2章では、中小企業の実際の価格設定行動に焦点を当てて更に分析を行った。その結果を見ると、中小企業であっても、技術力等により商品を差別化できている場合や販路を複数持つ場合に、強い価格交渉力を持てることを示している。 「ばらつき」に加えて、今回の分析を貫く視点は、「バブル崩壊後に生じた経済構造の変化により、中小企業と様々なステークホルダーとの関係がどのように変化したか」というものである。 今回は、第2部第3章で金融機関との関係、第3部第1章、第2章で取引を通じた企業間の関係を扱った。加えて、第3部第3章では中小企業における人的資本の蓄積に生じた変化を取り上げた。これらの章における分析からは、近年の経済構造の変化に伴って、大きな変化が生じた部分と、変化が期待されながら未だ生じていない部分が見られる。 第3部第1章では、中小企業において「メッシュ化」は現実に起きており、取引先企業数が増加している。一方、メッシュ化によって滞るとの懸念のある取引先との情報流通については、取引先の増加と同時に情報のやり取りが増大しているとの結果が得られている。また、長期継続的な取引は減少したが、重量取引をはじめとする従来の取引慣行の残存により、技術が価格に適正に転嫁されないといった状況も見られる。 同様に、金融機関との関係を調べた第2部第3章においても、複数行取引が主流という構造には変化はないが、金融機関同士の競争の激化から取引行数が増加している。また、規模の大きな中小企業における金融機関への満足度が高まる一方で、小規模企業の資金調達においては金融機関との接触頻度が大きく低下しているとの変化が見られる。 人的資本形成については、1990年代以降の雇用のリストラを通じて、キーパーソンやプロデューサー型人材など経営を支える人材が中小企業から失われている上、近年の労働市場逼迫によって、中小企業がますます優秀な人材を確保しにくくなっているとの変化が見られる。 |
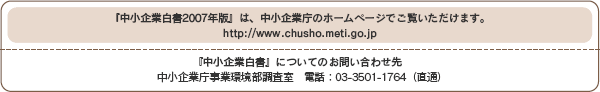 |
(2007年6月 vol.311) |