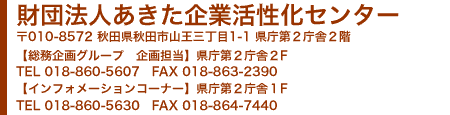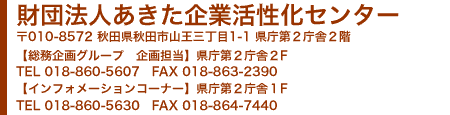|
  社名: 株式会社ヤマダフーズ本社: 〒019-1301 仙北郡美郷町野荒町字街道の上279 TEL.0182-37-2246 FAX.0182-36-2289 茨城工場: 〒300-1283 茨城県牛久市奥原町字司塙台1753 TEL.0298-75-2111 FAX.0298-30-9111 遊心庵: 〒013-0105 横手市平鹿町浅舞字中東144 TEL.0182-24-3811 FAX.0182-24-3812 URL http://www.yamadafoods.co.jp/ |
| 
日本の元祖健康食品ともいえる納豆。納豆発祥の地と言われる秋田県南から、全国、世界へ納豆をはじめとする食品を送り出している株式会社ヤマダフーズ。力強いリーダーシップで会社を引っ張る代表取締役 山田清繁氏にお話を伺った。
納豆発祥の地から創業
永保3年(西暦1083年)に清原真衡と家衡の家督争いを発端に、現在の横手市金沢公園を舞台に起こった「後三年の役」の際、俵に詰め馬に背負わせた大豆が偶然発酵したのが納豆の誕生であると言われている。以降、現在まで日本の食卓に欠かせない健康食品として愛されてきた納豆を、秋田から全国へ供給してきたのが(株)ヤマダフーズである。
1900年代半ばにGHQと日本政府によって農地解放が行われ、日本の7割の農地が地主から小作農へ売られたともいわれている。地域の地主であった山田家もほとんどの農地を失い新たな出発を強いられたこの時、現在の社長である山田清繁氏の父、山田清助氏は、地域で盛んに作られていた自家製納豆に目を付け、これを商売にしようと見よう見まねで納豆づくりを始めたそうだ。自転車の荷台に納豆を積み、大曲、横手へと売り歩いた。
「当時、納豆は発酵ムラがあって当たり前の食品で、私も親父が作った納豆から発酵していない部分を取り除く作業をよく手伝っていました。農家の長男ですから、家を継ぐのが当たり前と思って、東京の学校を卒業後、納豆づくりを手伝いました。そこで、もっと合理的、科学的な納豆づくりがしたいと考え、研究を始めたのです。安定した品質で大量に供給することが可能になれば、商売は大きく飛躍すると分かっていましたから」。山田氏自ら全国の大学や研究機関から情報を集め、納豆の発酵の仕組みを研究してきた。そして、約15年かかって昭和50年に自社開発の納豆製造プラント工場を完成させたのだった。長く家内的につくられていた食品を、同社が流通に耐えうる“おはよう納豆”へと成長させたのだ。
長期的戦略で販路を拡大
県内全域に着々と販売網を拡大させていった同社であったが、山田氏は、昭和57年に代表取締役社長に就任するずっと前から販路を首都圏に広げたいと戦略を練っていた。「当時、首都圏の消費者が買いたいのは、納豆発祥の地“秋田の納豆”ではなく、“水戸の納豆”だったんです。そこで、敢えて茨城県に生産の場を構えようと決めました。さらに、工場が出来たときに充分な販売網が整っていなければ意味がありませんから、毎日、秋田から冷蔵車を走らせ地道な営業活動を続けました。23年かかって、満を持して茨城工場を竣工。もちろん地元の反発は激しいものがありましたが、今では地元住民の方々に愛され、行政なども応援してくれていると感じます」。
平成8年に完成した茨城工場は、もちろん全て自社開発の生産ライン。徹底した合理化、IT化が図られ、コスト競争では絶対の自信があると山田氏は胸を張る。現在は、24時間フル稼働状態で、首都圏のどこへ行っても同社の納豆が手に入るまでになった。長期的視野を持ち、大きな目標に地道な活動で挑んだ山田氏のねばり強さは納豆そのものだ。
また、販路拡大と同時に、様々なニーズに対応できる商品を揃えるため、原料である大豆づくり、製品開発、品質管理にも徹底してこだわってきた。アメリカ、カナダ、中国の契約農場で栽培した大豆を、研究を重ねてたどり着いた最良の加工方法で製品化する。驚くことに、生産ラインだけでなく、原料の大豆や納豆菌のほとんどが自社開発なのだそうだ。 |
|