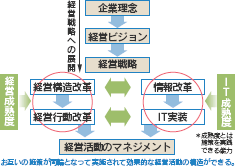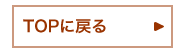|
いまやITの活用は経営のインフラとなり、その有効活用は企業の命運を左右するといっても過言ではないでしょう。ITを有効活用して、企業の競争力を強化し、顧客価値の創造を行い、収益(利益)を上げる担い手として貢献を期待される人がITコンサルタントであり、その人材がITコーディネータ(以下ITC)です。 現在、企業を取り巻く経営環境は、外部・内部環境とも激しく変化し、技術の進歩・発展、顧客要求の多様化、地域間格差やグローバル化した企業間競争の激化で企業経営の活力が低迷し、環境の変化に適合した企業経営の舵取りが大変に難しい社会になってきております。
一方ではITの急速な進歩により、ブロードバンド化やWebマーケティングによる商慣習の環境も大きく変貌し、激化した経営環境に適合した企業経営のスピード化や経営力の向上・収益向上のための経営改革がますます要求されてきております。 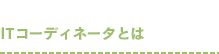
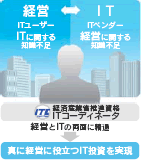 ITCは経営者の思いや企業理念、企業価値観を理解・把握し経営者の立場に立って「経営とITを橋渡し」し、真に経営に役立つIT化投資を推進・支援するプロフェッショナルです。 ITCは経営者の思いや企業理念、企業価値観を理解・把握し経営者の立場に立って「経営とITを橋渡し」し、真に経営に役立つIT化投資を推進・支援するプロフェッショナルです。
このITCの使命は、経営環境の変化を企業の経営者と共有して、経営者の視点で①革新的な、経営戦略の策定を支援する、②経営戦略目標を達成するための戦略的なIT化投資支援を通して、経営改革を支援することです。
つまりは、経営者の立場に立って、経営力を向上させるIT化投資を考えられるコンサルタントがITCなのです。

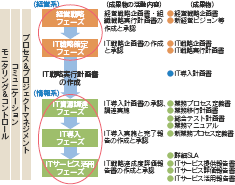 経営戦略とITCプロセスにあるように、ITCのプロセスでは経営系の上流工程から情報系の下流工程へ展開を図るわけですが、特に経営系の視点が、企業の経営戦略を立案・策定して、経営戦略目標を達成するために最も重要なプロセスとなります。 経営戦略とITCプロセスにあるように、ITCのプロセスでは経営系の上流工程から情報系の下流工程へ展開を図るわけですが、特に経営系の視点が、企業の経営戦略を立案・策定して、経営戦略目標を達成するために最も重要なプロセスとなります。
とりもなおさず、今までのIT導入の失敗事例は経営系の重要な視点が欠落して、情報系の視点だけでIT導入の比較検討や費用対効果の提案のみの、IT導入ありきが前提であったように思います。
ITベンダに在籍し、ITソリューションを展開してきましたが、あくまでもITリテラシ(利活用)のあるべき姿のソリューションであったと痛感しています。
 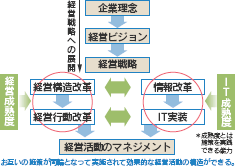
経営戦略への展開では、これら経営系の視点が経営構造改革と情報改革(業務改革)の施策が両輪となって実施されて、はじめて効率的な経営活動の構造ができ、より明確な経営活動のマネジメントができあがるのです。
すなわち、経営改革と業務改革をIT活用により、実現することがIT経営となります。
IT経営をコンサルティングするITCは、経営者の立場に立って、企業経営のあるべき姿をより明確に具体化(可視化)して競争優位の原則を保ちながら、IT化のビジネスプロセス(業務プロセス)の見直しや改革・改善をしながら、新ビジネスモデルを確立して収益向上につなげ、IT経営の全体最適化を図ることが期待されています。
さて、ここで経営力を向上させるために経営戦略を策定するうえで、特に重要な収益向上の基本的な考え方を整理してみます。 収益向上の基本的な考え方
①顧客価値の創造ができる戦略であること
顧客価値の創造とはお客様が儲かること。すなわちお客様に満足されること。
②ベストプラクティスを導入すること
最善の業務プロセスを導入すること。
③コアコンピタンスを持つこと
お客様の価値を創造する同業他社と違った独自の企業競争力を有すること。
コアコンピタンス強化の戦略を打ち出すこと。
④選択と集中を行うこと
顧客価値を最大に伸ばす分野と、そうでない分野の経営資源の選択と集中を図ること。
⑤集中した経営資源が最適資源配分されること
戦略は顧客価値最大と経営効率最大が均衡する交点として、最適な資源配分とすること。
⑥戦略と業務プロセスの整合性を保つこと
業務プロセスは経営戦略のもとにその戦略遂行のためのプロセスと整合性を持って創るべきもの。
⑦知識共有と継続的な学習が必要である
新しい業務プロセスを効率的に運用するため、継続的な社員教育や実施後の改善・改良提案を共有し、改善対策が適切にされること。
⑧継続的な改善が必要である
改善は継続的に実施されて効果が発揮される。経営環境の変化のスピードが早くなり、戦略性を見据えた継続的な改善が要求される。
⑨収益性が不可欠である
収益の伴わない戦略は立案する意味がない。 |
経営戦略の立案やIT経営のご相談はITC秋田にご連絡ください。
*参考文献資料
・ITCAのITコーディネータ(ITC)プロセスガイドライン Ver1,1
・ITコーディネータ IT経営の最新知識 井上正和著。 | 
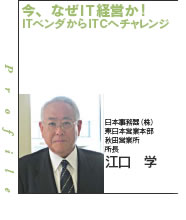
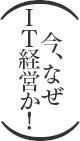
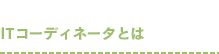


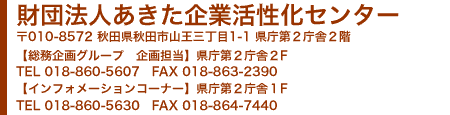
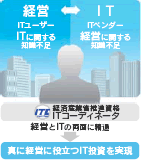 ITCは経営者の思いや企業理念、企業価値観を理解・把握し経営者の立場に立って「経営とITを橋渡し」し、真に経営に役立つIT化投資を推進・支援するプロフェッショナルです。
ITCは経営者の思いや企業理念、企業価値観を理解・把握し経営者の立場に立って「経営とITを橋渡し」し、真に経営に役立つIT化投資を推進・支援するプロフェッショナルです。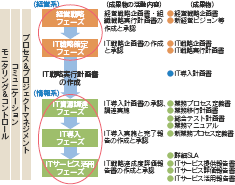 経営戦略とITCプロセスにあるように、ITCのプロセスでは経営系の上流工程から情報系の下流工程へ展開を図るわけですが、特に経営系の視点が、企業の経営戦略を立案・策定して、経営戦略目標を達成するために最も重要なプロセスとなります。
経営戦略とITCプロセスにあるように、ITCのプロセスでは経営系の上流工程から情報系の下流工程へ展開を図るわけですが、特に経営系の視点が、企業の経営戦略を立案・策定して、経営戦略目標を達成するために最も重要なプロセスとなります。