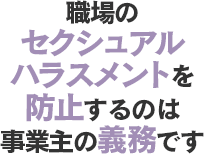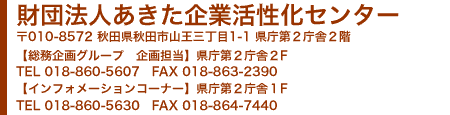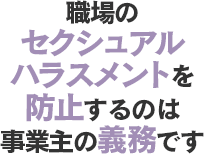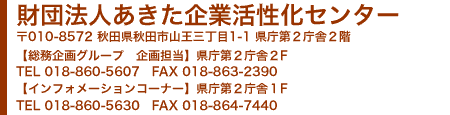|
「職場に向かうことを考えただけで、体が震えてきて胸がひどく苦しくなるんです。仕事そのものは大好きなんですが、職場にはとても行けそうにありません。もう辞めるしかないと…ずっとそればかり考えています」相談者は涙で声を詰まらせながら、やっと少しずつ話をしてくれました。こういった相談を聴き、援助するのが私の仕事です。
実際にセクシュアルハラスメントが起きてしまった場合、その最悪の結末は被害を受けた人が職場を辞めなければならない事態に陥ってしまうことです。その後の生活の保障はどうなるのでしょう。これまで積み重ねてきた知識や教養はどうなるのでしょう。キャリアも途切れてしまいます。また、セクシュアルハラスメントを防げなかった職場の志気も下がってしまうことでしょう。このような事態に陥らないための責任は、事業主の皆さんにあります。
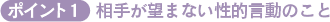 セクシュアルハラスメント(以下セクハラ)の定義には、表現にいくらかの違いはあっても、必ず「相手が」という言葉が入ります。相手が望まない性的言動、相手の意に反する性的言動、相手を不快にする性的言動などと定義されます。つまり、言動を受け取る側が望んでいない、ということが大切な要件となるわけです。 バスや電車の中で足を踏まれている場面を想像してみましょう。「痛い!」と声を上げるのは足を踏まれている側の人です。踏んでいる人は言われるまで気付いてすらいないことも多いでしょう。痛くないからです。何かの拍子に足が外れれば、踏んでいた事実さえわからなくなってしまいます。しかし、踏まれていた人にとっては痛みも不快さも残ります。「痛い!」と声を上げ、相手の行為を指摘できるのは痛みのある側なのです。セクハラもこれに似ていて、セクハラを受けた人こそが「嫌だ、不快だ」と言い、相手の行為に「No!」を突きつけられるわけです。 しかしこれは言動を起こした側から見ると、自分の問題であることに気付きにくいということです。自分の言動がまわりにどう受け取られるのか、自分自身を見つめる厳しい目がないと、私たちはいつでも加害者になってしまいます。
 「綺麗な足だねぇ」「君はスタイルがいいね」「ごちそうするから遊ばない?」などといった、日常よく耳にするセリフ。言っている側は「褒めているんだ」「いやらしい気持ちじゃない」と言い訳します。では、このようなセリフを職場の上司や大切な取引先の娘さんに言えるでしょうか?相手が上司や取引先の娘さんになると同じセリフが言えなくなるのは、立場が逆転するからではないでしょうか。 この例でわかるように、セクハラはほとんどの場合、力関係に差があるところで起きます。前述の「対価型セクハラ」はその典型であり、解雇や配置転換、降格は権力を持っていなければできません。相手を自分より低く見ているからセクハラは起こるのです。別の言い方をすれば、弱い立場の人に対してセクハラをしているのです。そして弱い立場にいる人からすれば、拒否もしにくいし「No!」という意思表示も難しいのです。
 職場の環境を整備し、気持ちよく働いてもらう責任は事業主にあります。とすれば、セクハラ防止も事業主を中心に、組織全体の理解と協力のもとで進めていかなければならないものでしょう。被害を訴えている人の自助努力や、当事者同士だけで解決することではないのです。 セクハラという言葉が一般的になったのは1989年ころで、この年の流行語大賞になっています。ちょうど女性が“職場の華”扱いから腰を据えて働きだした時期と一致します。その後、セクハラの裁判例が蓄積され、また法的整備も徐々になされ、現在はセクハラ対策の措置が事業主の義務となりました。セクハラという言葉は今や誰でも知っていて、職場だけではなく学校や医療機関など様々なところで対策を講じるようになり、社会全体の認知度が高まってきました。さらに、企業では近年「コンプライアンス(法令遵守)」という考え方が広まり、その一環としてセクハラ防止に力を入れるようになってきました。もはや「そんなの関係ない」とはいえない状況にあります。
セクハラ対策は予防が一番大切です。就業規則などの文書に規定すること、研修や社内報による啓発、相談窓口をつくること(外部委託でもかまわない)、適切迅速な対応ができる体制をつくることなどが第一歩です。ニュースで取り上げられる派手なセクハラ事件より、自分により身近なセクハラをなくし、ひとりひとりが大切に尊重される気持ちのいい職場づくりを目指していきましょう。
イラスト出典:「Open sesame! ひらけごま」制作 プラウ・プロジェクト
|