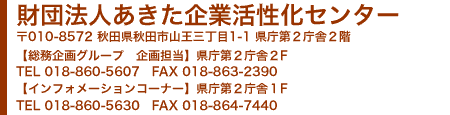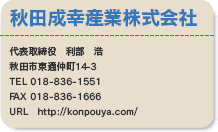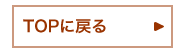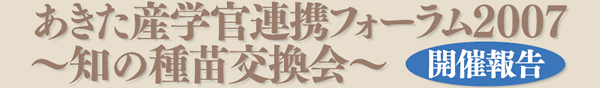 |
 財団法人あきた企業活性化センターは、大学等のシーズと産業界のニーズのマッチング促進のため、産学官連携に関する取組への理解を深める「あきた産学官連携フォーラム2007〜知の種苗交換会〜」を、平成19年11月13日(火)、14日(水)の二日間、秋田市(秋田市拠点センターアルヴェ)において開催いたしました。今年度は、独立行政法人科学技術振興機構JSTイノベーションサテライト岩手などの主催による「第1回北東北地域イノベーションフォーラム」との併催となり、より多くの参加者を集めることができました。1日目の概要をご紹介いたします。 財団法人あきた企業活性化センターは、大学等のシーズと産業界のニーズのマッチング促進のため、産学官連携に関する取組への理解を深める「あきた産学官連携フォーラム2007〜知の種苗交換会〜」を、平成19年11月13日(火)、14日(水)の二日間、秋田市(秋田市拠点センターアルヴェ)において開催いたしました。今年度は、独立行政法人科学技術振興機構JSTイノベーションサテライト岩手などの主催による「第1回北東北地域イノベーションフォーラム」との併催となり、より多くの参加者を集めることができました。1日目の概要をご紹介いたします。 |
|
|
 若手研究者の意欲を喚起することにより、優れた若手研究者が持続的に輩出され、新産業・新事業の創出に資することを目的に今年度創設された賞です。今年度の受賞者は、秋田大学医学部教授 佐々木雄彦さん。研究テーマは「細胞膜リン脂質による生体調節機構の解明と創薬への応用」です。 若手研究者の意欲を喚起することにより、優れた若手研究者が持続的に輩出され、新産業・新事業の創出に資することを目的に今年度創設された賞です。今年度の受賞者は、秋田大学医学部教授 佐々木雄彦さん。研究テーマは「細胞膜リン脂質による生体調節機構の解明と創薬への応用」です。 |
|
|
|
講師:株式会社タニタ 取締役 開発・体重科学研究所担当 佐藤 等 氏 【内容抜粋】 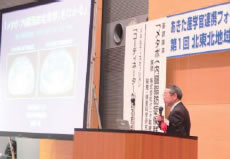 日本人の死亡原因の多くを占める心疾患や脳血管疾患などの循環器系疾患を引き起こす原因は、肥満に起因する動脈硬化です。男性の内臓脂肪症候群は年々増加傾向にあり、厚生労働省は来春以降、メタボリック症候群対策として特定検診・保健指導を実施する施策を示しています。肥満を測定するBMI値の算出法や評価基準、ウエスト周囲型の測定方法や評価については、まだばらつきがあり注意が必要です。また、数値やメジャーでの測定だけでは内臓脂肪の実態を把握するのは困難です。 日本人の死亡原因の多くを占める心疾患や脳血管疾患などの循環器系疾患を引き起こす原因は、肥満に起因する動脈硬化です。男性の内臓脂肪症候群は年々増加傾向にあり、厚生労働省は来春以降、メタボリック症候群対策として特定検診・保健指導を実施する施策を示しています。肥満を測定するBMI値の算出法や評価基準、ウエスト周囲型の測定方法や評価については、まだばらつきがあり注意が必要です。また、数値やメジャーでの測定だけでは内臓脂肪の実態を把握するのは困難です。(株)タニタでは非侵襲計測(体を傷つけずに計測する方法)の機器を開発・製造しています。腹部誘導型測定器は、もともと障害者向けに開発したベッド型の内臓脂肪計測器で、サイズ計測、電極を用いたインピーダンス(電気抵抗)計測により脂肪を測定します。量産準備段階にあります。血圧計や食事管理に有効な血糖計も開発・製造しています。 メタボ予防には生活習慣を変えることが必要です。紹介した機器の他、カロリースケールや歩数計など様々な計測器を使用することでモチベーションを維持できます。日本肥満学会では、体重3キロ、ウエスト3センチの減量を推奨する「3・3運動」を展開しています。減量に王道なし。食事・運動の管理の為のモチベーション維持が成功の鍵です。 |
|
|
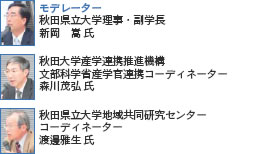 |
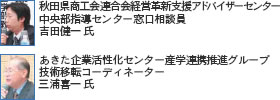 |
|
【内容抜粋】 |
| 森川 | : | 自分が企業にいるときは敷居が高いと感じていました。企業は最終的な段階になってやっと大学に相談に来られるので、日ごろから気軽に情報交換できる環境整備が必要ですね。 |
| 渡邊 | : | 確かに敷居は高いかもしれませんが、コーディネーターとしていろいろな機会を捕え企業の皆さまに会っていきたいと考えております。 |
| 吉田 | : | 小さな企業は大学とどう付き合えばいいのか分からずにいるようです。特に新しい分野に挑戦したいと考えている企業が情報収集段階で大学を活用できれば効果は大きいでしょう。 |
| 三浦 | : | 中小企業は短期で即効性のある情報や技術を必要としていて、時間を掛けても高度な成果を目指す大学研究とズレが生じることも。地域全体の産業振興を目指す上では、大きな違いは無いはずですから、工夫してどんどん敷居を低くし、みんなで協働していきたい。 |
| 新岡 | : | 現在では、どこの大学にも産学連携の担当窓口があり、今後、より親切な支援体勢が整っていくでしょうから、企業さんに積極的に利用していただきたいですね。 |
|
|
| 三浦 | : | ニーズオリエンテッドというか、産業界のニーズをしっかり掘り起こすことがまず大事。 |
| 吉田 | : | 事業化の責任は企業側にあるというような責任の所在を明確にすることが、シーズとニーズのマッチングをスムーズにするのではないでしょうか。 |
| 渡邊 | : | 大学の先生が企業のコンサルタント的な役割をして、定期的に相談に乗ってくれれば企業にとって大変効果があるだろうと思います。 |
| 森川 | : | 事業化が見込めるシーズは広く公開して欲しいですね。そして、企業側のニーズを十分に吸い上げて、マッチングを図っていきたいですね。 |
| 新岡 | : | 失敗経験のある企業の方が何もしない企業より伸びるという統計結果もありますし、恐れず挑戦していただきたいと思います。 |
|
|
| 渡邊 | : | 県民性よりも、いかに研究・開発に対する意識の高い企業と経営者を増やしていけるかが大きいと思います。そのために、あきた企業活性化センターや商工会連合会などがどう動いてくれるか期待したいです。 |
| 吉田 | : | なかなか本音を明かしてくれない経営者が多いのは感じます。支援者として、社長さんの懐に入って本音の付き合いをすることを心がけていますね。 |
| 三浦 | : | 安易に県民性を評価基準にせず、実態をもっと良く見て欲しい。一度敗れた者が立ち上がる再挑戦の力は大変強く、大いに期待できると思います。 |
| 森川 | : | 見栄張り、口が重いなどの傾向はあるかもしれませんが、産学連携においては、切れ目のない持続的な支援をすることが良い成果を生むポイントでは。 |
|
|
| 渡邊 | : | まずは与えられた課題、役割を遂行するということだと思います。 |
| 三浦 | : | 広範な知識、理解力を持って産学の橋渡しをするのがコーディネーター。提案やアドバイスでお役に立ちたいですね。 |
| 新岡 | : | 企業自身の体力や、熱心なコーディネーターが持続的に支援すること、大学側がニーズを拾い上げて製品化まで関係することなどが連携成功のポイント。そのために、大学も企業もコーディネーターを上手に活用することでしょう。新しい製品を生むしっかりとしたコミュニティを築くため、産学官の仲間を増やしていきましょう。 |
|
第2日目には、共同研究事例発表、成果発表、シーズ発表の全10テーマが発表されたほか、「北東北地域イノベーションフォーラム」では技術シーズ発表として、秋田高専、秋田大学、秋田県立大学、弘前大学、岩手大学から発表があり、産学官連携への取組と、その成果や可能性について関心を集めました。 |
|
10月号でご紹介した経営改革総合支援事業による支援企業をご紹介します。財団法人あきた企業活性化センターは県内企業の経営革新・経営改革のための取組を応援しています。 |
|
 部品や製品の工場からの出荷時や商品の移動等におけるキズや破損の防止、商品価値維持等のため、今やあらゆる製品に使われる梱包用資材。梱包用資材はいわば産業を支える縁の下の力持ちといえる。 部品や製品の工場からの出荷時や商品の移動等におけるキズや破損の防止、商品価値維持等のため、今やあらゆる製品に使われる梱包用資材。梱包用資材はいわば産業を支える縁の下の力持ちといえる。この梱包用資材の販売を発展戦略に掲げ経営改革を進めている企業が秋田成幸産業株式会社である。同社は、梱包資材の卸・小売販売や物流機器・消耗品類の販売を行っていた前身の成幸産業株式会社秋田営業所を、1988年(昭和63年)に利部氏が引き継ぎ独立法人化した企業である。 梱包用資材は様々な産業において需要が見込める製品であるが、一方では、使用後に処分される消耗品であるため単価自体低く、顧客の購入単価もさほど大きくない。そのため、売上を伸ばすためにはより多くの顧客を確保する必要がある。 引き継いだ当初は顧客数が少なく経営も厳しい状況であったが、年々多くの仕入れ先と繋がりを持ちながらメーカー直送方式の安い値段の設定と約2万種類という商品取扱を武器として、秋田市近郊や県北地域を中心に積極的に営業を展開し、大館市、能代市、八戸市と次々に事業部を立ち上げ、新たな顧客を開拓した。その結果、売り上げが当初の約10倍まで拡大している。 このように経営が安定してきたものの、営業マンの知識・経験に基づく営業だけでは、市場が県内近郊に限られ販路拡大が思うように進まないという課題があった。更なる販路開拓を進めるためには、別の手法も考える必要があった。 そこで、同社は、「ITを活用した新たな販売促進と新規販路拡大事業」をテーマとした経営改革計画を策定し、平成17年度から経営改革総合支援事業(フェニックスプラン21)の補助事業を活用して、インターネットを活用した全国展開を進めることとした。補助事業では、専門技術者を確保しながらインターネット通信販売専用サイトを構築し、平成17年11月にインターネットサイト「梱包屋どっとこむ」を開設した。当サイトでは、蓄積された仕入のノウハウを活かした安い価格設定で、紐・テープ類や梱包材のほか、梱包機器や運搬用台車、輪ゴム、手袋まで梱包に関する多種多様な商品を「プロ用・業務用資材」として全国に提供している。 インターネット販売事業を開始する前の取引先の数は、県内や近隣県を中心に約1,000社であったが、今では北海道利尻島から沖縄県まで日本全国約1,800社に上り、そのうちネット登録の企業数は現在約300社と年々増え、確実に販路が拡大している。ネット販売による売上げが全体に占める割合はまだ少ないものの、全体の売上げが伸びている中で、ネット販売も確実な成長が見込まれている。 「今後は、関西方面へもサイトの広告宣伝を強化し全国からのネット登録企業を更に増やしたい。また、売り上げの8割が秋田市以北の県内企業であることから県南地域へも取引を拡大させたい」と同社は更なる発展戦略を描いている。 |
(2007年12月 vol.317) |