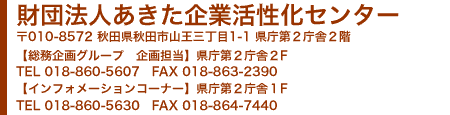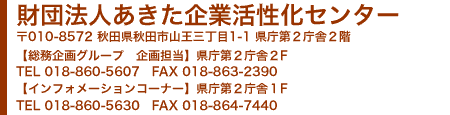|

社名: 株式会社マルユ本社:〒012-0107 湯沢市稲庭町字稲庭167-1 TEL.0183-43-2111 FAX.0183-43-2658 よこてシティホール
(株式会社玉姫グループ秋田支社) 〒013-0062 横手市駅南2丁目3-14 TEL.0182-33-4441 FAX.0182-36-4441 HP URL: http://www.yokote-cityhall.com/ |
| 
湯沢市稲庭(旧稲川町)は、古くから地場産業の盛んな地域。その地で、葬祭用の祭壇を生産してきた株式会社マルユが、平成18年1月、横手市に葬祭会館“よこてシティホール”を開館し、冠婚葬祭の総合プロデュース業へと大きく事業を展開させた。代表取締役社長の 齊藤雄太郎 氏 にお話を伺った。
稲川の職人たち
株式会社マルユが本社を置く旧稲川町は、全国的に人気を獲得した稲庭うどんや、近年、デザイン商品の開発に取り組んでいる川連漆器の産地として、古くから堅実に技を育み地場産業を守ってきた土地。川連塗りの技術を応用した川連仏壇(秋田仏壇)は、最盛期の昭和50〜60年代には年間35,000本もの仏壇を全国へ出荷していた。同社は、川連仏壇の創始者である阿部雄二氏の弟である齊藤雄蔵氏が昭和30年に仏壇の彫刻業から創業し、葬祭用の祭壇を生産し東北全域に出荷してきた。
木の香りに包まれた稲庭の工場に足を踏み入れると、切り出しや加工、組立に黙々と作業する職人の姿があった。現在、稲庭の本社工場の従業員15名のほか、自宅で彫刻を専門に作業している職人3名が同社の製造を支えている。
「私どもはこれまで、祭壇を葬祭業者に卸すのが主でした。中国などの安い産地が台頭する現在も、繊細な彫刻技術で、よそには負けない商品を作っています。それでも、これから企業としてもっともっと成長するために新しい挑戦をしたのです。以前から、自社生産の祭壇を使って地元の寺院や自宅での葬祭をお手伝いさせていただいていたのですが、3年前ベルコさんから総合的な冠婚葬祭事業についてお声掛けいただいたんです。」
新しい冠婚葬祭サービスを提供
株式会社ベルコが、「グループ会社として秋田県で冠婚葬祭事業を大きく展開しないか」と声をかけてくれたのだそうだ。祭壇の取引で築いた信頼関係があったからこそだ。その要請と期待を受け、玉姫グループとして互助会制度の販売を開始すると同時に、横手市に総合的にきめ細かなサービスを提供する“よこてシティホール”を開館させるに至った。
同社の互助会制度の特長は何より適正な価格だという。
「私たちには、自社生産の祭壇をご提供できるという最大の強みがあります。これにより、月々の小さな掛金と、ご葬儀一式18万円(月掛金1,500円×120回の掛金納入を前提とした基本価格)という、業界では低い価格設定での商品提供が可能なのです。また、葬祭だけでなく、婚礼のお手伝いもさせていただきます。近隣の婚礼会場と契約しておりますので、冠婚葬祭を総合的にお手伝いさせていただけます。」
感動プロデュース!!
“よこてシティホール”には、250名収容可能な大ホールと150名収容可能な中ホールがあり、仕切りを外しエントランスまで開放すると最大650名まで収容できるスペースになる。ほかに、ガラス越しにご家族が宿泊して付き添える安置室、ゆっくり過ごせるように浴室と洗面を備えた宿泊可能な和室が2部屋。また、隣の厨房で調理したばかりの温かいお料理を提供できる食事室。ご家族や葬祭の参加者が落ち着いて故人とお別れできるよう、充実した空間となっている。
そして、それらの設備を活かすのが同社のスタッフだ。互助会の会員制度は会員家族と生前から数年に渡ってお付き合いするもの。会員家族と直に顔を合わせて営業に当たる齊藤克文専務の言葉から、会員にとって頼れる身近な存在でありたいという想いが伝わる。
「家族が亡くなりましたので…」と電話を掛ける相手が顔の分かる葬祭業者であれば、ご家族の方に安心していただけると考えます。私たちは、生前から、たとえば、通常は葬儀に使用するホールでミニコンサートなどの催し物を実施し会員様に足を運んでいただくなど、身近なお付き合いをさせていただけるよう努めております。「任せたい」と思っていただける信頼を得たいですね。」
齊藤社長はじめとするスタッフが目指すのは、故人の思い出を参加者みんなで共有してもらい、感動してもらえる、感謝祭のような葬祭サービスだという。現在、県南を中心として6,300世帯の互助会会員を獲得し、一月平均20件の葬祭を行っている。社長は、「冠婚葬祭はまだ可能性のある市場だと思います。皆様に「よかった」と言っていただけるよう一層頑張ります」と目を輝かせた。
同社は、平成17年度から当センターの経営改革総合支援事業の補助金を活用し、人材育成、専門技術者の雇用、顧客管理システムの導入、広報に取り組んできた。
そのときの安心をこれからもプロデュースしてほしい。 |
|