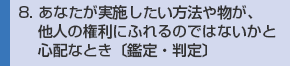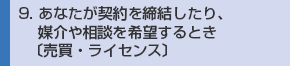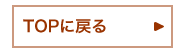|
|
「独自に開発した製品の利益を守りたい」「特許製品を広く販売したい」「ほかの企業が自社の模倣ではないか」。知的創造物に関する疑問や問題を抱えている企業の強い味方になるのが、“知的財産権”と、その保護・活用の専門家である“弁理士”です。 秋田県は、平成20年3月3日、日本弁理士会協力協定を締結しました(平成20年3月3日〜平成22年3月31日)。知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興を目指し以下の協力事項が確認され、今後、日本弁理士会と協力し県内中小企業の知的財産権に関する取組をサポートしていきます。 |
|
|
|
1 知的財産の普及啓発及び知的財産にかかる知識を有する人材の育成に関する事項 2 知的財産の相談に関する事項 3 知的財産の活用に関する事項 4 その他、地域産業の振興のための知的財産の保護と活用に関する事項 |
|
|
|
1 知的財産セミナー(秋田県、あきた企業活性化センター、日本弁理士会 共催) 2 知的財産相談会( 〃 ) 3 知財目利き委員会(評価対象の分野に合わせた弁理士を委員として派遣) |
知財目利き委員会とは? 県内大学・公設試験研究機関等で出願済みの特許を評価する委員会です。研究側で課題となっている知財関連予算や人材不足を補い、特許維持管理の効率化と技術移転の促進を図っています。(財)あきた企業活性化センターが事務を担当しています |
|
|
|
たいへんな労力をかけ開発した技術や製品の利益を、模倣や盗用から守ることができる権利が知的財産権です。そのうち、企業活動に深く関わる、技術に関する権利を産業財産権と分類します。 |
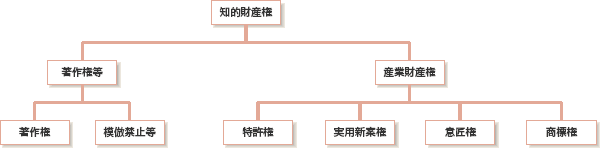 |
|
弁理士は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、の手続きを代理することができる国家資格者です。知的財産を生み出した方にとって、有利な内容でそれを権利化できるよう、調査やアドバイスを行い書類を作成し特許庁に提出します。また、権利の侵害に関しては弁護士と協力して訴訟に対応します。具体的には、次のような場面で弁理士を活用することができます。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
弁理士との協力により知的財産権を取得・活用することで、中小企業等の皆様には次のような利益が期待できます。「たいしたものじゃない」と考えてしまう前に、弁理士をはじめとする専門家に相談してみてはいかがでしょうか。技術や製品が、大きな利益を生むかもしれません。 |
|
|
|
(1)知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権)の譲渡による利益 (2)知的財産権に基づくライセンス契約に基づく収益 (3)知的財産権を担保とする借金 |
|
|
|
(1)出願中を含め他社の参入を妨害する参入障壁による利益 ;類似品が短期間に出現するのを防ぎ、シェア拡大 (2)特許等の表示による消費者心理をくすぐる宣伝広告による利益 (3)ある程度の価格決定権を有する利益 (4)製品メーカーに売り込みを有利にする利益 |
|
|
|
(1)ライセンス先の製品の宣伝を通じて自社製品の売り上げ増につながる利益 (2)非類似の分野での他者の宣伝による宣伝相乗効果による利益 (3)営業秘密(ノウハウ)による品質担保を商標でにおわすことによる広告効果 |
| |
|
|
|
知的財産権のうち、三浦電子株式会社も取得した特許の取得までの手続きの流れについて、10ページをご覧ください。出願から方式審査、審査請求、審査、特許査定と特許庁による手続きを通過すると、登録となります。その間、特許庁から補正や拒絶などが示され、申請をより正確なものに作り上げることが必要になります。「特許庁に根気よく通い、面談を重ねることでコツが分かってきます。諦めずに、アドバイスを貰うつもりで特許庁に足を運ぶことが大事ではないかと思います」と、三浦社長(三浦電子株式会社)。 千里の道も一歩から。そこにある財産が有効な権利になるかもしれません。 |
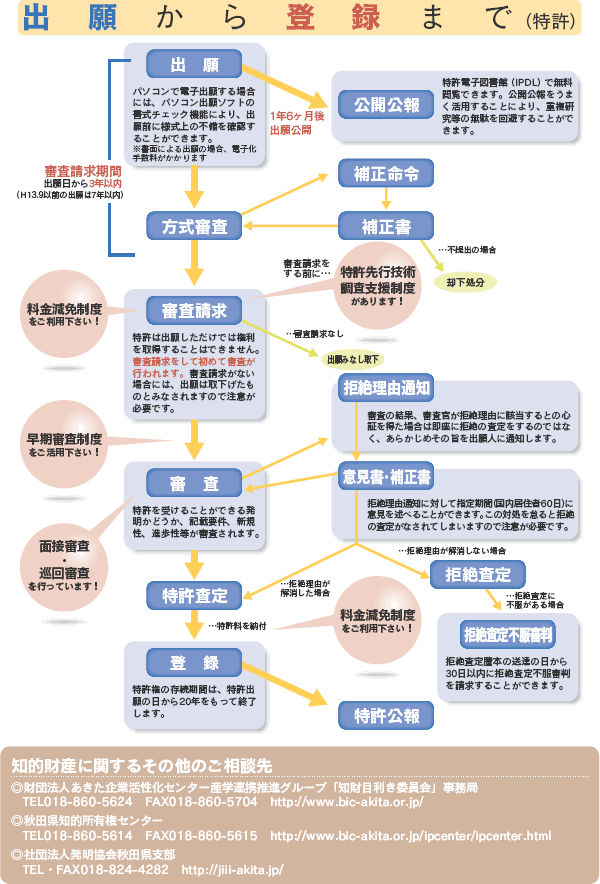 |
(2008年4月 vol.321) |
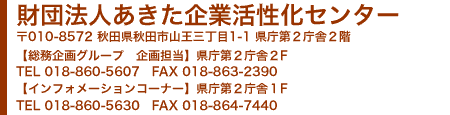
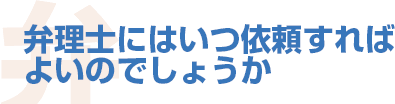
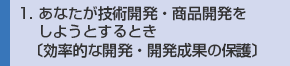
 a.新しい発明や考案、あるいは改良をしても、特許権や実用新案権として権利をとっておかないと、他人の実施を阻止できません。
a.新しい発明や考案、あるいは改良をしても、特許権や実用新案権として権利をとっておかないと、他人の実施を阻止できません。 弁理士は、どのようにすれば広い範囲の権利をとることができるかを検討し、意匠図面(必要によっては意匠写真)を作成して出願します。
弁理士は、どのようにすれば広い範囲の権利をとることができるかを検討し、意匠図面(必要によっては意匠写真)を作成して出願します。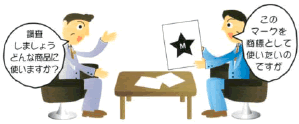 弁理士は、あなたの希望するマーク(商標)が登録に適するものであるかどうかを判断するとともに、必要に応じてそのマークと同一又は類似のものが、既に登録又は出願されていないかどうかを調査します。そして、あなたの商品又はサービスが商標法で定められたどの分類に属するかを判断して出願をします。
弁理士は、あなたの希望するマーク(商標)が登録に適するものであるかどうかを判断するとともに、必要に応じてそのマークと同一又は類似のものが、既に登録又は出願されていないかどうかを調査します。そして、あなたの商品又はサービスが商標法で定められたどの分類に属するかを判断して出願をします。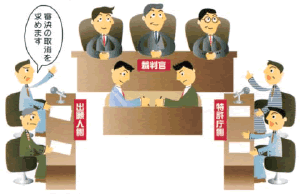 a.審判の請求
a.審判の請求 a.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品について、関税定率法に定める輸入差止申立手続及び認定手続きに関する権利者の代理を行い、あなたの権利を侵害する物品の輸入が差止められるようにします。
a.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品について、関税定率法に定める輸入差止申立手続及び認定手続きに関する権利者の代理を行い、あなたの権利を侵害する物品の輸入が差止められるようにします。