
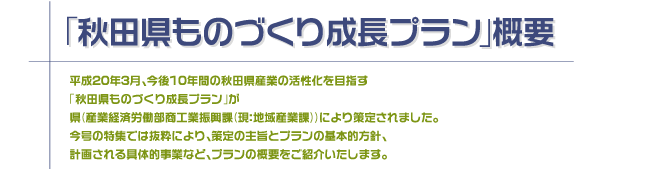
![]()
1.プラン策定の目的
本プランは、工業振興に係る長期的ビジョンである「秋田ものづくりビジョン」(計画期間:平成11年度から概ね10年間)及び短期実施計画としての「秋田県工業振興アクションプラン」(計画期間:平成17年度〜平成19年度)の後継プランとして、社会経済構造の変革や技術革新の進展など、本県のものづくり産業を取り巻く環境の大きな変化を踏まえ、今後10年間の本県のものづくり産業の活性化と持続的発展を目指す長期的ビジョンと、これに基づいて平成20年度から3年間の工業振興に係る実施計画を一体的に策定するものです。
2.プランの位置付け
本プランは、「あきた21総合計画」における「ものづくり産業」の振興に係わる分野の基本方針を明らかにする計画として位置付け、主に「あきた21総合計画」の基本目標の一つである「産業が力強く前進する秋田」に基づいた政策「産業の技術力・競争力の源となる科学技術基盤の形成」「活力のある秋田の創造に向けた産業の振興」で展開される施策・事業について具体的な推進方策を示すものとします。
3.プランの計画期間
 |
 |
本プランは、計画期間を平成20年度から平成29年度までの10年間とします。また、第1期の実施計画については、平成20年度から平成22年度までの3年間とします。
4.計画の進捗管理と見直し
本プランは、計画の実効性について検証を行い、様々な状況の変化に対応して弾力的に運用できるように、毎年度の進捗管理と見直しを実施していきます。
![]()
1.本県ものづくり産業の現状
(1)県内総生産
平成17年度秋田県県民経済計算年報によると、平成17年度の県内総生産は名目で3兆6,947億円で、産業別では、第1次産業が1,225億円(構成比3.3%)、第2次産業が8,247億円(同22.3%)、第3次産業が2兆8,628億円(同77.5%)となっています。第2次産業のうち製造業は、全体の13.9%となっています。県内総生産の構成比の推移をみると、第1次、第2次産業が減少し、第3次産業が増加してきていますが、製造業を取り出すと、平成16、17年と増加に転じています。
(2)製造品出荷額等
平成18年の製造業の製造品出荷額等は、1兆5,856億円で、5年前と比較して6.2%増加しています。平成13年以降の減少傾向から平成16年、17年と増加に転じ、平成18年には前年比13.3%と大幅に増加しました。これには、電子部品・デバイス関連製品の出荷額増加が大きく影響しているものと考えられます。同関連産業は県内の製造品出荷額等の41.7%を占め、本県のリーディング産業としての位置を占めています。
(3)事業所数、従業者数
本県の製造業における事業所数、従業者数は、ともに減少傾向にあり、年次別に見ると、平成13年、14年の落ち込みが激しく、県内の実質GDP成長率の動向と符合しています。業種別事業所数では、食料品、衣服関連の企業が一番多く400社台、次いで木材・木製品が200社台、窯業・土石、金属製品、一般機械、電子部品・デバイス等が100社台と続いています。また、従業者数では、大手の中核的企業が立地している電子部品・デバイス産業で約16,000人を数え突出して多く、次いで衣服、食料品の順となっています。
(4)粗付加価値額、労働生産性
本県の製造業における粗付加価値額(付加価値額+減価償却費)は、平成9年をピークに減少していましたが、製造品出荷額等と同様、平成16年から増加に転じ、平成18年には24.7%の大幅な増加となりました。但し、従業員一人当たりの付加価値額については、871万円と全国平均の約66.4%で、東北で第5位となっています。なお、全国集計の従業員一人当たりの付加価値額を業種別に見ると、化学工業、飲料・たばこ・飼料製造業、石油製品・石炭製品製造業、鉄鋼業の順となっています。
(5)地域別状況
県内の地域別状況を見ると、事業所数では多い順に、秋田周辺、大曲・仙北、湯沢・雄勝で、従業者数では、秋田周辺、本荘・由利地域、大曲・仙北となっています。また、製造品出荷額では本荘・由利が最も多く秋田周辺がそれに続いています。
本荘・由利地域では、電子部品・デバイス関連の大手企業が立地し、関連企業の集積があり、東北でも有数の産業集積区域となっています。
![]()
2.本県のものづくり産業の課題
(1)労働生産性、付加価値生産性の向上
本県製造業は、下請型、部品組立型の企業が多く、また、一人当たりの付加価値額が全国でも低位にあります。このため、地域特性を活かした付加価値の高い新事業の創出、適正な資源配分や作業プロセスの改善等により、労働生産性や付加価値生産性を向上させていくことが必要です。
(2)技術力の強化と人材の育成
自動車産業等のものづくりの分野においては、今後、受注を獲得するため、QCD(品質、コスト、納期)面で一定のレベルに達している必要があり、人材の育成等により、技術力や生産効率の向上を図り、競争力を強化していくことが不可欠です。また、本県で良質な人材を育成することは、企業競争力の強化や企業誘致にも資することになると考えます。
(3)技術経営力の強化
今後の製品開発、技術開発に関しては、部品製造に関わる中小企業も含めて、いかにして自社の経営資源を見直し・集中しながら、自社技術の強みを発揮して製品開発を行い、企業経営に活かしていくかといった「技術経営」の考え方が求められてきています。また、こうした企業経営を進めていくためには、製品開発のための産学官連携、販路開拓、知的財産権の取得・活用、IT活用等が重要になってきます。
(4)環境を意識したものづくり
輸送機や家電関連産業では、既に環境対応の考え方が広く普及しており、消費者側にも浸透してきていることから、本県におけるものづくり産業においても、独自性の高いリサイクル産業の事業化や既存製品における生産プロセス最適化によるエネルギーのコストダウン、環境対応新製品の開発等にチャレンジしていくことが期待されます。
(5)事業承継問題
経営者の高齢化や後継者の減少等により事業の継続が困難になったり、経営に影響を与える可能性があります。本県においては、少子高齢化が全国で最も早いテンポで進行している中、すぐれた技術を有する事業所の減少を抑えるような、新たな発想からの事業承継が必要であると考えます。
(6)地域資源の活用と産業の集積 (クラスター形成)の促進
地域の雇用を確保し、経済の活性化を図るためには、地域の産業特性に配慮した産業集積を高めていくことが有効と考えます。本県においても、国の関係施策等を活用し、地域特性を活かした産業集積の形成、経済の活性化に取り組む必要があると考えます。
(7)次世代の本県産業を担う新産業の育成
海外との競争が激化する中で、今後は国際競争力のある分野で新たな産業を育成していく必要があります。本県におけるこれまでの産業集積や産業基盤等のポテンシャルを踏まえた産業分野や今後有望な産業と言われている分野の育成にも積極的に取り組んでいく必要があります。
![]()
1.本県のものづくり産業の目指す姿
| 質の高いものづくり人材・経営による「技術・人材立県あきた」の実現と 日本海対岸諸国を中心とした物流・生産ネットワークの構築による国内のものづくり拠点の形成 |
本県のものづくり産業にとってこれからの10年は、少子高齢化や資源の需給逼迫など様々な制約が高まっていく社会経済環境の中で、選択と集中をますます進めるなど経営の構造的な改革を進め、技術・技能を活かした攻めの経営へと企業体質を転換しながら、新しい高齢化社会に挑戦し、次の成長につなげていく重要な時期となるものと考えます。今後は、本県の勤勉な県民性や豊かな自然環境を活かした“技術・人材立県”として力強いものづくり産業の成長をめざしていくことが必要です。
このため、これからのキーワードである環境等を意識した質の高い人材と独自の技術を財産としながら、足腰が強く(景気の好不況に左右されにくい)、柔軟性の高い(産業構造の転換等に対する素早い対応ができる)ものづくり産業の着実な発展を実現していくことにより、広く雇用を確保するとともに、持続的経済成長と豊かさを実感できる社会の実現に寄与していきます。
このような本県のものづくり産業の成長により、本県が10年後には、日本海対岸諸国の中国、韓国、ロシア等の国々との国際的分業において、我が国における物流・生産の交流拠点としての役割を果たしていくよう、官民一体となった取組を進めていきます。
2.ものづくり産業の目指す4つの基本的方針
(1)技術スキルの高い産業人材の確保・育成による企業競争力の強化
県内企業は、今後、自ら積極的にコア技術を親企業に提案したり、また、事業転換等により新しい事業分野へ進出する等の意欲的な経営姿勢が求められる状況となってきています。このため、継続的に経営品質の向上に取り組み、また、ものづくりへの関心が高く、新たな技術ニーズに対して適応力が高い人材を育成し、「受身から自立へ」と企業価値を高めていく取組に対して積極的に支援していきます。
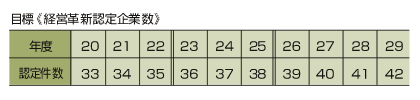
(2)労働生産性の向上と付加価値の高い生産活動の展開
少子高齢化による労働力人口の減少や技能伝承等の課題を克服し、ものづくり産業を持続的に成長させていくためには、労働生産性を高めながら、生産改善に関する意識を高め、付加価値の高い生産活動を目指していくことが肝要です。このため、生産効率の向上等「経営品質」の向上に努めながら、大学や公設試験研究機関との産学官連携による地域発イノベーションを効率的・持続的に生み出していくための連携を強化していきます。
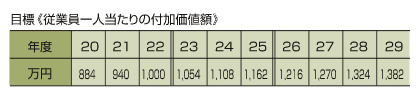
(3)地域特性を踏まえた将来性の高い 産業分野の集積の促進
地域には、これまで培ってきた事業活動における魅力が備わっており、こうした地域特性を発揮しながら、電子部品・デバイス、自動車等の輸送機関連産業や資源リサイクル産業及び地域における農林水産資源を活用した食品関連産業等の将来有望な産業の集積を高め、本県のリーディング産業として育成・支援していきます。
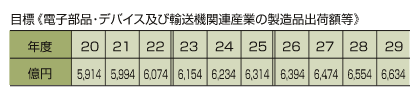
(4)産業集積の促進と企業誘致の推進
産業集積のためには、人材、用地、産業インフラ等の立地環境の総合的な整備が必要ですが、こうした環境を整備することにより、企業誘致はもとより、地元企業の新規立地や増設を促進し、県内における多極的な産業構造の形成を目指します。また、秋田港の物流機能の高度化等の産業インフラの整備促進により、今後進展が予想されるわが国と東アジアとの国際的分業ネットワークにおいて、本県が日本海対岸諸国との物流や生産拠点としての役割を果たしていくことが期待できるものと考えます。
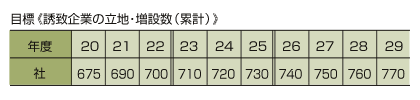
![]()
1.ものづくり成長プランの全体構想と第1期アクションプランの事業体系
本プランにおいて、本県が我が国のものづくり産業の拠点として発展していくため、計画期間を3期に分け、事業の進捗状況を検証しながら、戦略的で着実な目標達成に向けた取組を展開していくこととします。なお、第2期、第3期計画の計画・目標については、それぞれ直前の期の最終年度に計画の進捗に対する検証を行い、その時々の経済環境やその時点での経済予測等を考慮して、必要な修正や施策の追加等を行うものとします。
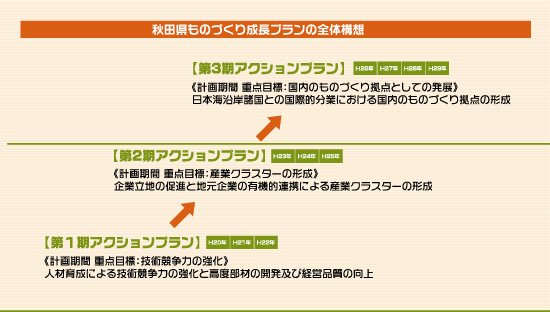
2.第1期アクションプランの具体的事業
| 人材育成による技術競争力の強化と高度部材の開発及び経営品質の向上 |
(1)技術スキルの高い産業人材の確保・育成による企業競争力の強化
(1)少子高齢化・グローバル化に対応した重点的・戦略的な産業人材の育成
(2)児童・生徒のものづくりに対する関心の向上と大学、高専、工業高校生の実践的産業人材教育の推進
(3) 技能伝承と事業承継への積極的な取組
| 経営革新認定企業数(平成22年度35件) |
 (2)労働生産性の向上と付加価値の高い生産活動の展開
(2)労働生産性の向上と付加価値の高い生産活動の展開
(1)競争力の基盤としての経営品質の向上
(2)産学官連携と地域発イノベーションの創出
(3)意欲的な経営者への転換と技術経営の普及
| 従業員一人当たりの付加価値額(平成22年度1,000万円) |
 (3)地域特性を踏まえた有望な産業分野の集積促進
(3)地域特性を踏まえた有望な産業分野の集積促進
(1)本県のリーディング産業を目指す将来性の高い輸送機関連産業の集積促進
(2)地域特性を活かした産業の展開
(3)これからの成長が期待される産業への取組
(4)知的財産権の保護と活用
| 電子部品・デバイス及び輸送機関連産業の製造品出荷額等(平成22年度6,074億円) |
 (4)産業集積の促進と企業誘致の推進
(4)産業集積の促進と企業誘致の推進
(1)産業集積の促進
(2)立地環境の整備と企業誘致の推進
(3)誘致企業と地元企業との有機的連携の推進
| 誘致企業の立地・増設数(累計)(平成22年度700件) |
最後に、プランの中で、計画の実現に向けて企業に期待される役割が次のように記されています。
企業は、地域経済の担い手として、本県の経済発展と雇用確保に当たって中核的な役割が期待されます。今後のものづくり産業は、少子高齢化と経済のグローバル化の影響で、これまで経験しなかったような構造的な変革を迫られることになるものと考えます。このため、本プランのキーワードである技術力の強化と人材の育成を戦略の中核に据えて、一層意欲的な経営体質へと転換していくことが求められています。
| プランに関する お問い合わせ先 |
秋田県産業経済労働部地域産業課 〒010-8572 秋田市山王3-1-1 県庁第二庁舎3階 TEL.018-860-2241 FAX.018-860-3887 プランの全文が、県ホームページ「美の国あきたネット」からご覧いただけます。 http://www.pref.akita.lg.jp 美の国あきたホーム>組織別案内>産業経済労働部>地域産業課(旧商工業振興課) |
