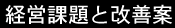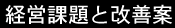- 歴史のある会社で、設備及びそれらを操作する技術基盤はしっかりしている。反面、現状からの脱却がうまくできていない。
良い時代が長かったのかもしれないが、受注比率が特定の会社に偏っている。このため危険分散が難しい体質になっている。むしろ今は、いろいろな業種業界で積極的な受注活動を行い、特定の波に影響されにくい体質に改善すべきである。また、現在は受注先が固定しているため、受注・納品処理がワン・パターンで、それ以外の得意先からの受注をうまく処理できる体制になっていない。従ってコンピュータシステムを構築する上では、色々な受注パターンに対応出来るシステムの構築を目指す必要がある。
- 工場からの情報収集(工数集計)はある程度できているが、継続的でない。またそのデータが見積り比較などに利用されていない。
「データは活用するためにあるのだ」ということ、継続して収集されたデータは、見積比較、工数予測、原価管理等に活用できるということを再確認することが必要である。
- 業務全体が特定の人物に頼っている。
受注から発注・納品に至るまで、特定の人が頭で管理していて、その人がいないと業務に支障をきたすほどの危険な状態にある。一日も早いシステム化が望まれる。
- 鉄構部と機械部の業務に融通性がないのはもったいない。
鉄構部と機械部を融合することによって、新たな営業展開が可能な状態にある。また、現在その必要性があっても、お互いが融通をきかしていない。一種の大企業病になっていることに気付くべきである。「この業務は誰がやる」といったことを決定する人、または機関を設ける必要がある。今後システム化が進むと、社内外の情報を適時にコンピュータに入力していかないとシステムが機能しなくなる。一日も早い横のつながりの確立が望まれる。
- 業務全体をコンピュータ化するにはパソコンの絶対数が足りない。
パソコンの台数が業務量に対して不足している。パソコンは一部の集計業務に使われているだけで、本来パソコンが最も力を発揮する業務は手作業で行われている。例えば、受注台帳等が手書きであるため、得意先別・納期別・受注残リストを毎日のように書き写している。この作業には受注金額・請求金額など計算業務が関わることから手書きでは非常に効率が悪く、さらに間違いが発生する元になっている。また、発注データの処理にはコンピュータを利用しているが、システム化されていないため検収・未検収の管理ができず、問題が発生してから発注先へ督促している。こうした事項を解決するためにも、システム化が必要である。
- 各業務が一元化されていない。社内でシステム化の必要性を感じていても、それを取りまとめてシステム構築に乗り出す人がいない。
業務全体を把握している人がいない。システム構築者は会社の仕組みを作る(これは経営者の仕事であるのだが)ことになるので、業務全体を効率化する心構えでシステム構築に取組むことが必要である。また、事務系の人たちが共通でわかるキー・データがない。部門によって必要なキーが違うためシステムを構築できないでいる。
|