 ― 地域活性化施設としての役割 ―
建設省が1993年に整備を始めた「道の駅」は、高速道路のパーキングエリアの機能を持った一般道路の施設である。都市間を結ぶ一般道路上に、休憩・案内情報などの施設を計画的に配置し、利用者の利便を図るとともに、地域おこしの拠点として整備しようというものである。
現在、上記で紹介した他にも多くの道の駅があり、10月1日にオープンした「てんのう」や、来年4月オープンを目指す「おがち」など、今後続々と新しい施設が誕生する予定である。
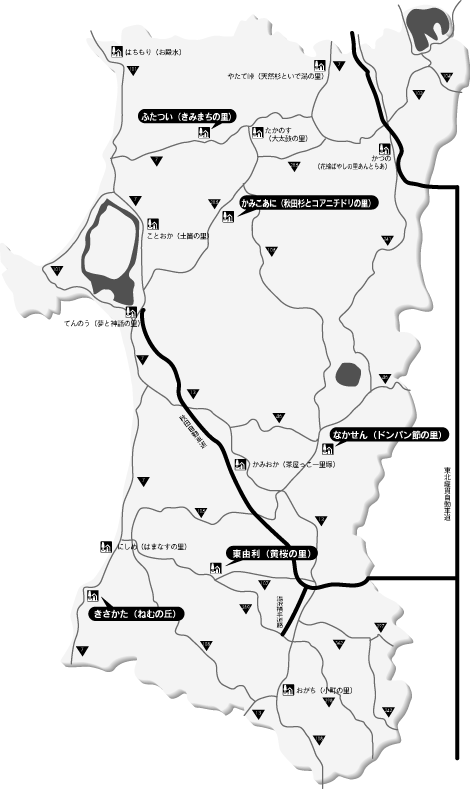
|

 ― 地域活性化施設としての役割 ―
建設省が1993年に整備を始めた「道の駅」は、高速道路のパーキングエリアの機能を持った一般道路の施設である。都市間を結ぶ一般道路上に、休憩・案内情報などの施設を計画的に配置し、利用者の利便を図るとともに、地域おこしの拠点として整備しようというものである。
現在、上記で紹介した他にも多くの道の駅があり、10月1日にオープンした「てんのう」や、来年4月オープンを目指す「おがち」など、今後続々と新しい施設が誕生する予定である。
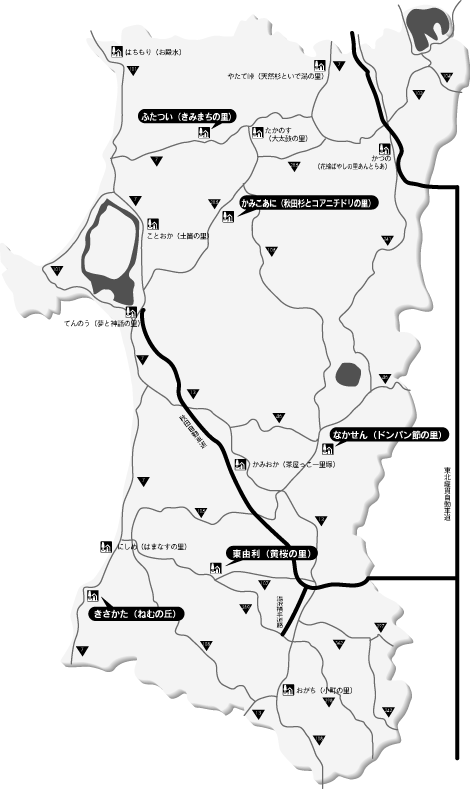
|
